2015年9月 4日
グラフェンp-n接合を用いた電子のビームスプリッタ動作の原理実証に世界で初めて成功 ~電子の量子光学研究が大きく加速~
日本電信電話株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鵜浦博夫、以下 NTT)は、CEA Saclayと共同で、グラフェン※1p-n接合※2を用いた電子のビームスプリッタ動作の原理実証に世界で初めて成功しました。量子光学の実験に必要な基本素子であるビームスプリッタが実現できたことで、グラフェンを用いた電子の量子光学研究が可能となります。
グラフェンは電子のコヒーレンス長※3が長く電子の量子光学実験に有用な材料と考えられていますが、量子光学の実験に必要な基本素子であるビームスプリッタを作製するのが困難であるとされてきました。共同研究グループはグラフェンp-n接合が電子のビームスプリッタとして動作することを提案し、層数均一性が高く伝導特性が良いグラフェンを大面積で生成する技術を利用して原理実証を行いました。このビームスプリッタとグラフェンにおける長いコヒーレンス長を利用することにより、これまで不可能だった複雑な干渉計の作製等が可能となるなど、電子の量子光学研究が大きく加速します。これにより、光子にはない電子間相互作用が電子のコヒーレンス損失に与える影響の評価や量子もつれ生成が実現され、固体中の量子情報伝達・処理が発展することが期待されます。
この成果は、2015年9月4日(英国時間)に英国科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」で公開されます。
1.研究の背景
量子光学とは、ビームスプリッタやミラーなどの光学素子を組み合わせた干渉計を用いて、光の粒子性、波動性を量子力学的に研究する分野です。ここで得られた知見を元に、光子を使った量子暗号や量子テレポテーションなどが提案、実証されてきました。一方、電子も光子と同様、粒子性および波動性を持つ量子であり干渉することが示されています。また、フェルミ粒子※4である電子とボーズ粒子※5である光子との干渉性の違いも示されてきました。電子と光子は、フェルミ粒子かボーズ粒子かという違いだけでなく、クーロン相互作用※6の有無という大きな違いもあります。クーロン相互作用は、それを通して電子の量子状態を制御できるというメリットがあり、これを利用した様々な量子デバイスが研究されています。その反面、クーロン相互作用は電子間や電子と不純物の間の散乱を引き起こし、電子のコヒーレンスを壊してしまうというデメリットもあります。
これまで電子の量子光学研究で最も良好な結果が得られているのは、砒化ガリウム(GaAs)と砒化アルミニウムガリウム(AlGaAs)の半導体ヘテロ構造※7中の2次元電子系に磁場を加えた時に現れる量子ホール効果※8を利用したものですが、電子のコヒーレンス長は10 µm程度が限界でした。この系では、ビームスプリッタは量子ポイントコンタクト※9と呼ばれる電子の透過確率が1/2となるような細いチャンネル(図1 左)を形成することにより実現されていますが、その構造が複雑であるため干渉計の大きさがコヒーレンス長と同程度となってしまい、実行できる研究は限られ、その成果は電子の量子性を実証するという基本的な段階に留まっていました。一方、特異な物性を示すことで近年注目を集めている2次元物質であるグラフェンでは、電子のコヒーレンス長が長いと考えられており、この性質を利用することにより、より詳細に量子性を調べたり、より高度な干渉計を作製したりすることが可能となります。しかし、グラフェンはバンドギャップがないため、電子を空乏化させて作製する量子ポイントコンタクトを利用したビームスプリッタが動作せず、グラフェンを用いた電子の量子光学実験は実現困難とされてきました。
これに対し、NTT物性科学基礎研究所(以下、NTT物性研)とCEA Saclayでは、グラフェンにおける新たな動作原理を持つビームスプリッタとしてp-n接合を利用したものを提案し、これまでに培ってきたグラフェン成長技術を利用して実証を進めてまいりました。
2.研究の成果
今回、NTT物性研とCEA Saclayは、グラフェンにおいてp-n接合を用いた電子のビームスプリッタを提案し、その原理実証に世界で初めて成功しました。グラフェンのp-n接合では、n領域とp領域の電流チャネルが混成し、例えばn領域から入射された電子はp-n接合中でn領域とp領域のエッジチャンネルに等確率で分配され、その出口で分岐します(図1 右)。この分配と分岐プロセスをビームスプリッタとして提案しました。
また、ビームスプリッタとしての動作を確認するため、電流のノイズ(ショットノイズ※10)を計測しました。ビームスプリッタとして動作する場合、p-n接合に入射された電子はランダムにn領域とp領域のエッジチャンネルに分配され、ショットノイズが発生します。今回の実験では、p-n接合が短い時、ビームスプリッタとして振る舞う場合に予想される大きさのショットノイズが観測され、p-n接合を長くしていくとその大きさが小さくなっていきました。この結果から、p-n接合における量子性損失の目安となるエネルギー緩和長は15 µmであることが求められ、15 µmより十分短いp-n接合はビームスプリッタとして動作することが実証されました。
図1 電子のビームスプリッタ
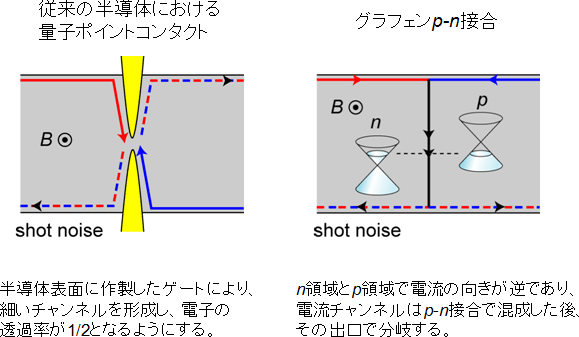
行った実験の説明
| <1> | 実験に用いた試料は炭化ケイ素(SiC)上に成長されたグラフェンを用いました。このグラフェンは均一にnドープされています。p-n接合を形成するために試料の半分を覆う表面ゲートを作製しました。この表面ゲートに負の電圧を加え、その直下にp型キャリアを誘起することにより、ゲートがない領域とある領域の境界にp-n接合を形成できます。今回の実験では、p-n接合の長さが5~100 µmの範囲で異なる5種類の試料を準備しました(図2)。 |
|---|
図2 大面積グラフェンを利用した試料の作製
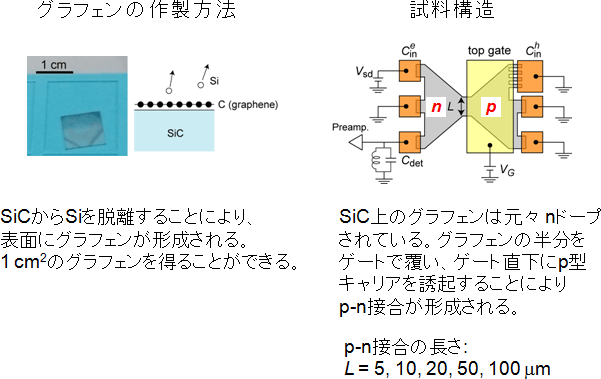
| <2> | グラフェンに垂直に磁場を加え、量子ホール効果となっている状態で実験しました。表面ゲート電圧の符号を変えることにより、p-n接合が形成されている状態と形成されていない状態を実現できます。これらの状態でショットノイズ測定を行い、p-n接合が形成されている時だけショットノイズが発生することを示しました。この結果は、確かにp-n接合で電子の分配が起きていることを示しています(図3)。 |
|---|
図3 p-n接合で発生するショットノイズ
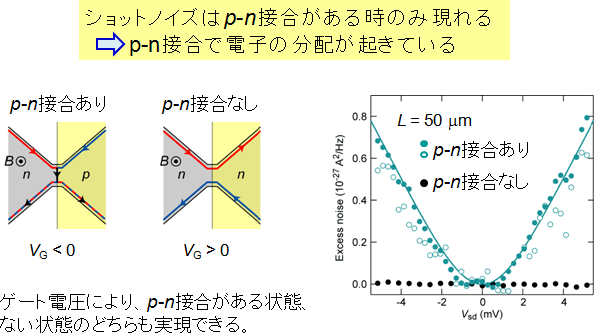
| <3> | p-n接合の長さが異なる試料で同様の測定を行い、ショットノイズの大きさがp-n接合を長くしていくと共に減少していく振る舞いを観測しました。この結果から、p-n接合中で量子性が保たれている目安となるエネルギー緩和長が15 µmであると求まりました。このエネルギー緩和長より短いp-n接合はビームスプリッタとして動作すると考えられます(図4)。 |
|---|
図4 p-n接合の長さを変えた時のノイズの変化
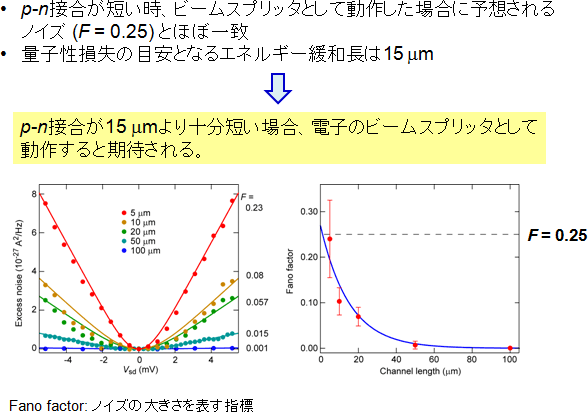
3.技術のポイント:グラフェン成長技術
一般的に、グラフェンはグラファイトから剥離することにより作製されていますが、試料サイズが最大で数十 µmに限定されるという欠点があります。これに対して、NTT物性研では、グラフェンを電子・光の素子材料として基礎物理からデバイスまで総合的に研究しており、層数均一性が高く、伝導特性が良いグラフェンを大面積で生成する技術を有しています。今回の実験では、この大面積である特徴を生かしてp-n接合の長さが異なる試料を作製しました。これにより、量子性損失の目安となるエネルギー緩和長を求めることが可能となりました。
4.今後の展開
グラフェンp-n接合によるビームスプリッタは、従来の半導体における量子ポイントコンタクトを用いたものより簡単な構造をしており、集積化が容易です。このビームスプリッタと、グラフェンにおける長いコヒーレンス長を利用することにより、これまで不可能だった実験が可能となります。ビームスプリッタを2つ組み合わせた様々な大きさの干渉計を作製し、コヒーレンス損失メカニズム、特に電子間相互作用の影響、を明らかにします。この知見を基に、より長いコヒーレンス長を得ることができると期待しています。さらに、多数のビームスプリッタを組み合わせることにより、電子の量子もつれの生成を目指します。
論文掲載情報
N. Kumada, F. D. Parmentier, H. Hibino, D. C. Glattli, and P. Roulleau
"Shot noise generated by graphene p-n junctions in the quantum Hall effect regime"
Nature Communications (2015).
用語解説
※1グラフェン炭素(C)原子が六角形格子構造上に並んだシート状の物質。移動度、光学応答・透明性、フレキシビリティ、化学的安定性等において優れた特性を持ち、基礎研究・応用研究両面から盛んに研究されている。特に本研究に関する特徴としては、有効質量が極めて軽いことに起因して、エッジチャンネル中の電子が散乱を受けづらく、さらに伝搬速度が速いという利点がある。このことから、コヒーレント長が長いと考えられている。 ※2p-n接合
p領域とn領域が接した領域。一般的な半導体ではバンドギャップが存在するため、p領域とn領域の間に空乏層が存在し、整流性を示す。一方、グラフェンではバンドギャップがないため、p領域とn領域が空間的に接した構造となり、一般の半導体とは大きく異なる伝導特性を示す。 ※3コヒーレンス長
量子が干渉可能な距離。量子は波の性質を持っているが、長距離伝搬する間に不純物との相互作用などにより波の位相が乱され干渉性を失う。コヒーレンス長は、量子が干渉性を失わず伝搬できる距離を表す。 ※4フェルミ粒子
スピンの値が1/2、3/2、5/2、...と半整数の値をとり、一つの量子状態に複数の粒子は存在できないという性質を持つ。電子、陽子、中性子などがフェルミ粒子に属する。 ※5ボーズ粒子
スピンの値が1、2、3、...と整数の値をとり、一つの量子状態に任意の数の粒子が存在できるという性質を持つ。光子などがボーズ粒子に属する。 ※6クーロン相互作用
電荷を持つ粒子の間に働く相互作用で、その力の大きさは粒子間の距離の2乗に反比例する。2つの粒子が持つ電荷が逆符号(プラスとマイナス)の場合は引力、同符号(プラス同士、マイナス同士)の場合は斥力となる。 ※7半導体ヘテロ構造
異なる半導体を接合させた層構造。半導体はそれぞれ固有のエネルギーバンド構造を持つが、異なる半導体を接合させることで、もとの半導体やその混晶にはない特性が得られる。半導体レーザや高電子移動度トランジスタなどで使われている。 ※8量子ホール効果
2次元電子系に垂直に磁場を加えた時に現れる現象。ホール抵抗が量子化され、縦抵抗がゼロとなる。この量子ホール効果状態では、電流は試料端に沿ったエッジチャンネル中を流れる。 ※9量子ポイントコンタクト
量子ポイントコンタクトとは、2つの導体に挟まれた狭い伝導チャンネルである。この量子ポイントコンタクトの幅を調整することにより、導体間の電子の透過確率を制御できる。 ※10ショットノイズ
電子の持つ電荷や光子の持つエネルギーに由来した電流や光強度に現れるノイズ。電子の持つ電荷は有限であり、電流が非常に小さい時、電子数の揺らぎに対応してショットノイズが現れる。
特記事項
なお、本研究成果と密接に関連する成果が、大阪大学、京都大学、物質・材料研究機構の共同研究グループから、同時に「Nature Communications」に発表されます。
本件に関するお問い合わせ先
日本電信電話株式会社
先端技術総合研究所 広報担当
a-info@lab.ntt.co.jp
TEL 046-240-5157
ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
NTT STORY
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。















