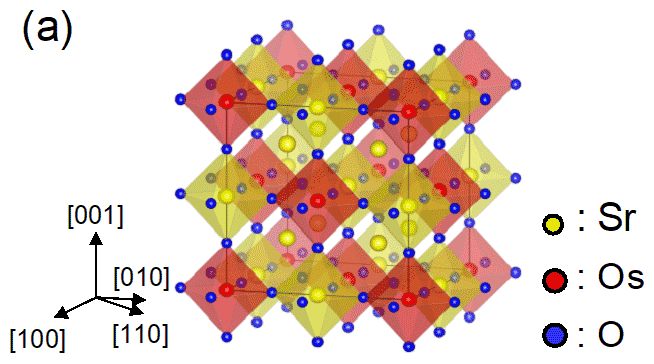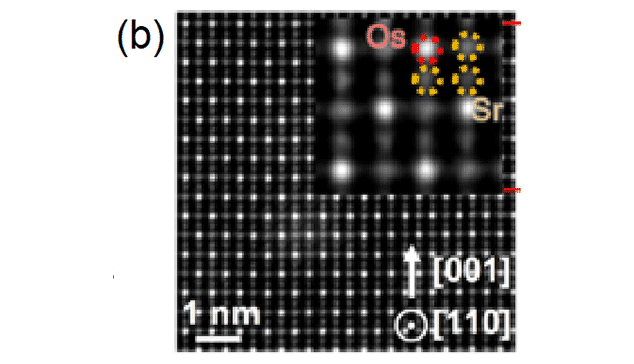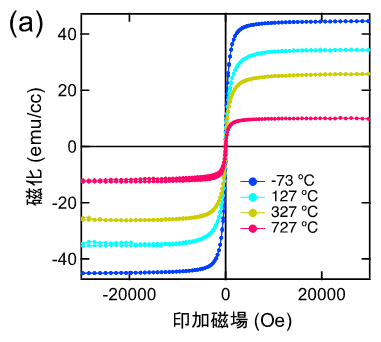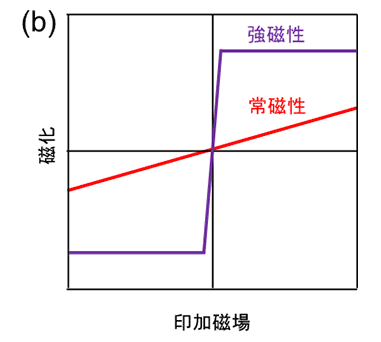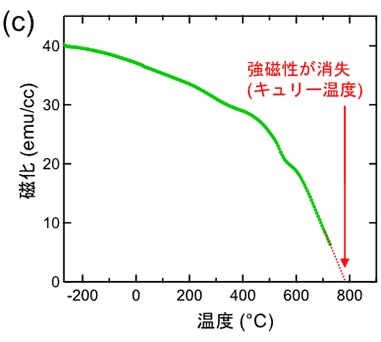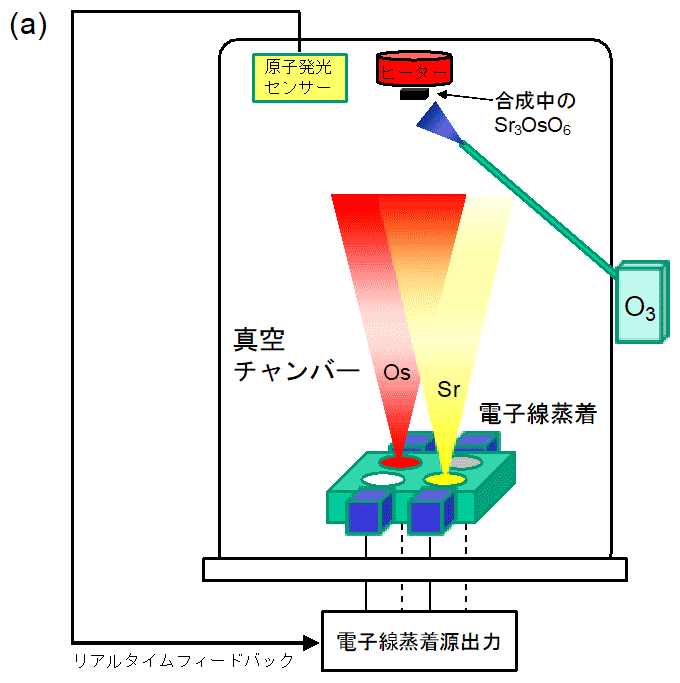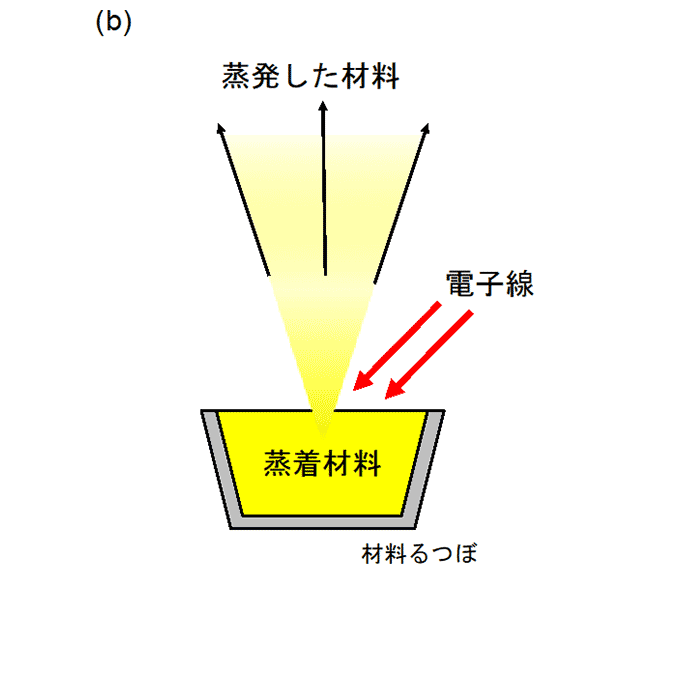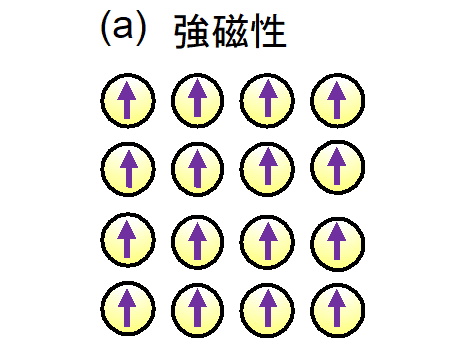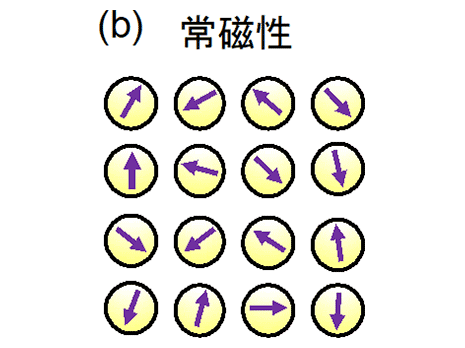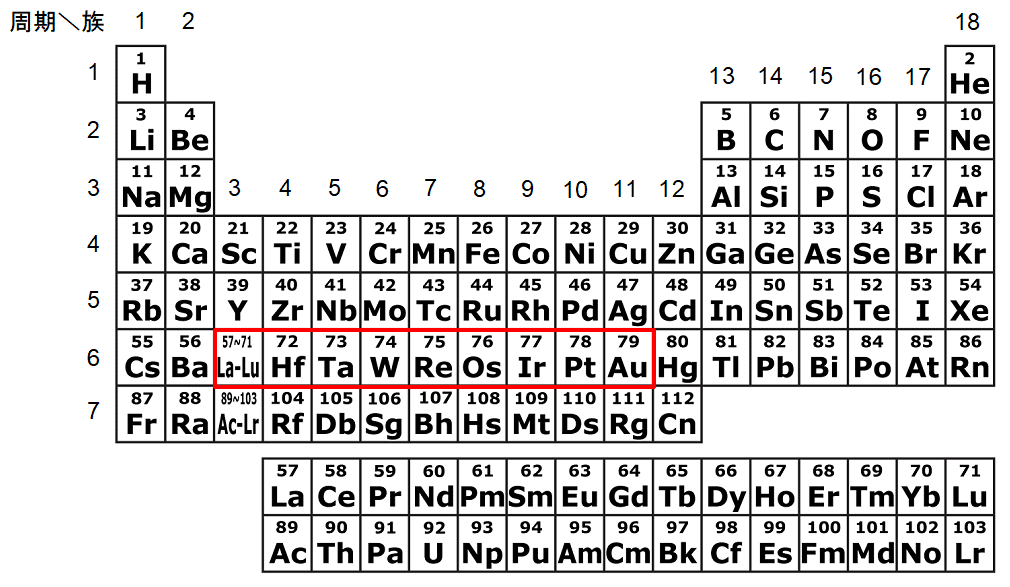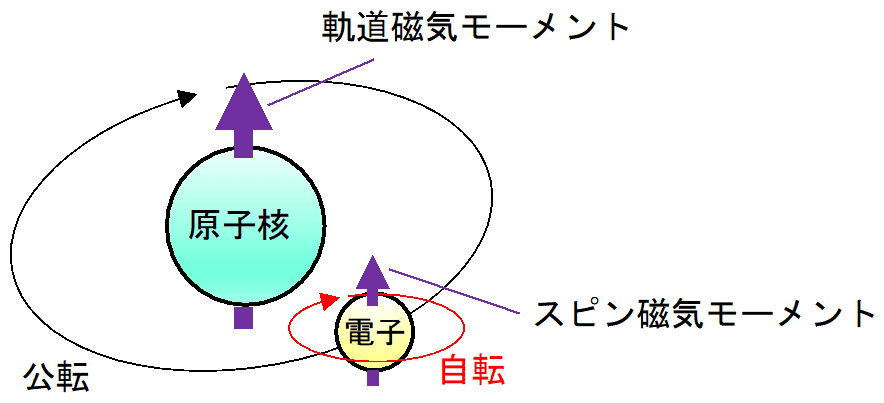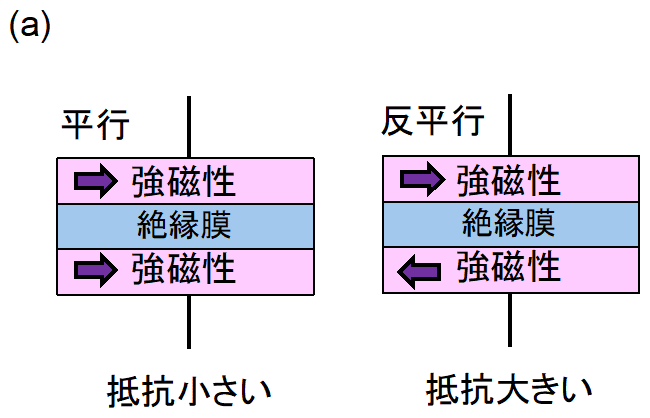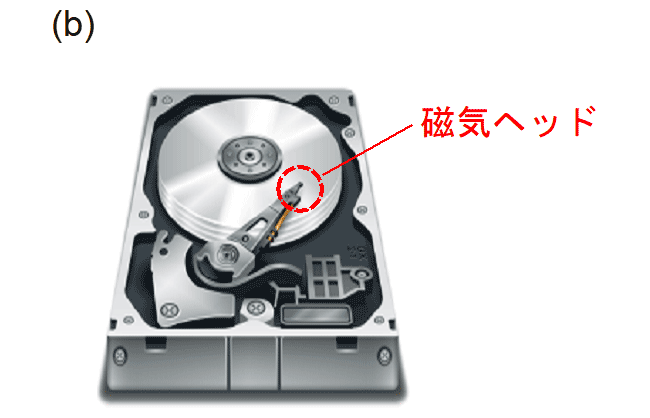2019年2月12日
日本電信電話株式会社
東京大学大学院理学系研究科
最高の強磁性転移温度を持つ新絶縁物質Sr3OsO6を創製
~88年ぶりに記録を更新~
日本電信電話株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:澤田 純、以下 NTT)は、電気を通さない物質(絶縁体)の中で、最高の温度(780℃以上)で磁石としての性質(強磁性※1)を示す新物質Sr3OsO6[Sr(ストロンチウム)、Os(オスミウム)、O(酸素)からなる物質]を世界で初めて合成・発見し、磁性発現の起源となる電子状態※2を、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 常行真司教授らの研究グループ(以下 東大)と共同で明らかにしました。
今回合成した物質は、88年ぶりに絶縁体の強磁性転移温度(キュリー温度※3)を更新するもので、長年の磁性材料研究の歴史を塗り替える成果です。この新物質の発見により、高い温度で強磁性が発現するメカニズムに関する基礎科学的な知見が得られました。また、現存する高温磁性材料のほとんどに鉄やコバルトが含まれるのに対し、新物質はこれらの元素を含まないため、磁性材料の開発に新機軸をもたらすと考えられます。さらに、Sr3OsO6は、素子化に適した単結晶薄膜※4の形で合成されました。そのため、室温~250℃程度の実用的な温度で安定に動作する、磁気ランダムアクセスメモリや磁気センサといった高機能磁気素子の開発につながるものと期待されます。
本成果は、英国科学雑誌「Nature Communications」2月12日号に掲載されます。
1.研究の背景
強磁性絶縁体※5には、人類が最初に発見した磁石で、方位磁針として使われた磁鉄鉱などがあります。それらは現在でも、永久磁石や高周波用素子として、スマートフォン、自動車、パソコンといったありとあらゆるものに使用され、テクノロジーの発展を根底から支えています。近年では、電子の持つ磁気的な性質と電気的な性質を同時に活用して素子の高速動作や低消費電力動作を実現するスピントロニクス素子の研究が盛んになり、この素子の材料としても強磁性絶縁体が有望視されています。
近年の電子化の潮流と相まって実用素子への要求性能は高まる一方であり、動作温度に関しては、室温にとどまらず200℃を超える高温での安定動作が求められています。しかしながら、磁気素子の高温での安定動作の可否を決める主要な因子であるキュリー温度は、1930年代のフェライト磁石※6開発以降、90年近く更新されておらず、高いキュリー温度を持つ次世代の強磁性絶縁体の実現と、その探索指針の構築が待たれていました。
2.研究の成果
NTT物性科学基礎研究所は、長年にわたり開発・蓄積してきた独自の酸化物合成技術によって、最高のキュリー温度を持つ新物質Sr3OsO6を世界に先駆けて合成・発見しました(図1)。磁化測定によって見積もられたキュリー温度は780℃を超え(図2)、これは、絶縁体のキュリー温度を88年ぶりに100℃以上更新する成果です。
また、東大と共同で行った密度汎関数理論※7に基づく計算により、Sr3OsO6の強磁性絶縁状態が、5d遷移元素※8であるOs(オスミウム)の大きなスピン軌道相互作用※9に由来することを明らかにしました。これは、高温での強磁性の発現機構に新たな知見を呈示するもので、学理の構築へ貢献するとともに、今後、スピン軌道相互作用が大きな元素を活用した新物質開発へとつながることが期待されます。
本物質は新物質であるだけでなく、素子化に向けた微細加工と相性の良い単結晶薄膜の形で合成されました。このため、室温以上の高温で安定に動作する磁気ランダムアクセスメモリや磁気センサといった、高機能磁気素子の開発につながるものと期待されます。
3.技術のポイント
高品質なSr3OsO6薄膜の合成
ダブルペロブスカイト※10と呼ばれる結晶構造(図1a)を持つSr3OsO6薄膜を、分子線エピタキシー法※11によって創製しました。高品質な薄膜を合成するには、合成時にSr3OsO6を構成するそれぞれの元素の供給量を精密に制御することが重要になります。従来、3000℃以上の融点を持つOs原子の供給量の精密制御は困難とされていましたが、供給する原子の量を原子からの発光を利用してモニタし、高出力電子線蒸着源の出力にリアルタイムでフィードバックすることにより、Sr原子とともにOs原子の供給量の精密制御に成功しました(図3)。この技術の確立により、原子レベルでSrとOsが規則的に配列した超高品質なSr3OsO6薄膜(図1b)の合成が可能となりました。
4.今後の展開
放射光施設※12などの利用で可能となる先進的な分光手法を用いて、新物質Sr3OsO6の電子状態に関するさらに詳細な知見を得ることで、強磁性体の学理の構築への貢献をめざします。また、高温で安定に動作する高機能磁気素子の実現へ向けて、Sr3OsO6を材料に用いた素子を作製し、トンネル磁気抵抗効果※13の実証などに取り組んでいきます。
用語解説
※1 強磁性 物質の原子が持つ磁化が整列し、物質全体として大きな磁化を持ち磁石として振る舞う性質のことです(図4a)。
※2 電子状態 1つずつ別々に真空中を運動する電子(自由電子)と異なり、固体中にある電子は、原子核に引きつけられる効果、電子同士の相互作用の効果などにより、それぞれの物質に固有の状態をとります。このような物質中での電子の状態を電子状態と呼びます。物質の性質は電子状態によって決定されるため、電子状態の解明は、材料開発の成否を左右する非常に重要なプロセスです。
※3 キュリー温度 その温度以上では磁石の性質(強磁性)が失われる温度。キュリー温度以下では、磁石の原子が持つ磁化が整列しており、物質全体として大きな磁化を持ちますが(図4a)、キュリー温度以上では原子の磁化の向きがバラバラとなった常磁性になり、磁石としての性質を失います(図4b)。
※4 単結晶薄膜 原子が格子を組んで規則正しく配列している固体を結晶と呼びます。このような結晶化した試料のうち、どの部分においても原子配列が同じで、構造の乱れの少ないものは単結晶と呼ばれます。次に試料の厚みが原子層厚から概ね数十マイクロメートル(1マイクロメートル = 1×10-6 メートル)と薄いものは薄膜(はくまく)と呼ばれます。単結晶薄膜は、それを支える土台となる単結晶(基板と呼ばれます)の上に作製されます。本研究では、厚さ300ナノメートル(1ナノメートル = 1×10-9 メートル)のSr3OsO6薄膜を、SrTiO3の単結晶基板上で合成しました。素子化へ向けた微細加工を行うためには、物質をナノメートル単位の厚さを持った単結晶薄膜の形で合成することが必要不可欠です。
※5 強磁性絶縁体 磁石には電気を通すものと通さないものがあり、後者を強磁性絶縁体と呼びます。
※6 フェライト磁石 1930年代に日本で開発、工業化された現在世界で最も大量に使用されている強磁性絶縁体です。酸化鉄を主成分にコバルトやニッケル、マンガンなどが混合されているものが多くあります。
※7 密度汎関数理論 電子の電荷密度n(r)が空間座標rの関数として正しく与えられれば、物質中の電子の持つエネルギーがn(r)から計算できるという理論のことです。電子の電荷密度n(r)自体が座標rの関数であり、エネルギーはその密度の関数となることから汎関数(関数の関数)の名が冠されています。この理論に基づき、実験データを用いずに電子の振る舞いを決定する基本方程式から、物質の電子状態を予測することが出来ます。
※8 5d遷移元素 周期表で、第3族元素から第11族元素の間に存在する元素を遷移元素と呼びますが、その中でも第6周期に属するものです(図5)。周期表の下の方に位置する元素の方がスピン軌道相互作用※9が大きいため、Os(オスミウム)はFe(鉄)やCo(コバルト)よりも大きなスピン軌道相互作用を持ちます。身近な貴金属であるAu(金)やPt(プラチナ)なども5d遷移元素です。Os(オスミウム)は、Ru(ルテニウム)やIr(イリジウム)との合金の形で、万年筆のペン先に使用されています。
※9 スピン軌道相互作用 原子核の周りの電子の公転によって生じる軌道磁気モーメントと、電子の自転によって生じるスピン磁気モーメントの間の相互作用のことです(図6)。鉄を主成分とするフェライト磁石や、Fe(鉄)やCo(コバルト)そのものから作られた磁石ではスピン軌道相互作用の影響は小さいですが、Sr3OsO6では、5d遷移元素であるOsの大きなスピン軌道相互作用が重要な役割を果たしています。
※10 ダブルペロブスカイト 結晶の中では、原子が格子を組んで規則正しく配列しています。代表的な配列の仕方には名前がついており、「ダブルペロブスカイト構造」は結晶構造を表す名称の1つで、ペロブスカイト構造の仲間です。ペロブスカイト構造は、陽イオンを2つ以上含む酸化物に広く見られる結晶構造です。最近では、この構造を持つヨウ化物や塩化物が、次世代太陽電池として盛んに研究されています。
※11 分子線エピタキシー法 物質を構成する各元素を超高真空中でビーム状に供給し、土台となる加熱された基板上で反応させることにより、狙った物質の薄膜を作製する手法です(図3)。結晶構造の乱れが少ない高品質な薄膜を得ることができるため、一般的には、素子化などの目的で、既に存在する物質の高品質薄膜の作製に用いられます。本研究では、この手法を用いて、未知の新しい物質を作製しました。
※12 放射光施設 リング状の超高真空の通路に極めて高速に加速された電子を走らせ、磁場中でその加速度を変化させた際に放射される紫外線、X線などの光(シンクロトロン放射光)を利用できる実験施設です。様々な波長を持つ光が極めて高い強度で得られるため、目的に応じた波長の光を選択的に取り出し、高感度な分光測定による詳細な物性評価や分析が可能です。このため、材料開発を進める上で非常に重要な施設です。我が国では、Spring-8(播磨)、フォトンファクトリー(つくば)などの施設が広く利用されています。
※13 トンネル磁気抵抗効果 二つの強磁性体に挟まれた絶縁膜のトンネル抵抗が、強磁性体層の磁化の向きの平行、反平行により変化する現象です(図7a)。トンネル磁気抵抗効果はハードディスクドライブ(HDD)、磁気ランダムアクセスメモリ、磁気センサといった磁気素子へ幅広く応用されています(図7b)。
図
図1a:Sr3OsO6の結晶構造(ダブルペロブスカイト)の模式図。黄丸、赤丸、青丸はそれぞれSr、Os、O原子を示しています。図1b:合成したSr3OsO6の、原子レベルに拡大された顕微鏡像(透過型走査電子顕微鏡像)。[110]結晶方向からみた像で、原子レベルでSrとOsが図1aの通りに規則的に配列していることが分かります。
図2a:印加した磁場に対するSr3OsO6の磁化の変化。727℃という非常に高い温度でも磁化を示し、強磁性体の性質を有することが分かります。図2b:強磁性と、常磁性(磁石としての性質を失った状態)での印加した磁場に対する磁化の変化の模式図。図2c:Sr3OsO6の磁化の温度変化。印加磁場は2000 Oe。強磁性が消失するキュリー温度は780℃以上と推測されます。
図3a:本研究で用いた分子線エピタキシー装置の概念図。上部に取り付けられた原子発光センサでSrとOs原子の供給量をモニタリングし、各原子の供給量が常に一定となるように電子線蒸着の出力をリアルタイムでコントロールしています。図3b:電子線蒸着の概念図。高速の電子線を蒸着材料に衝突させ、材料の温度を上げて蒸発させます。ここで、電子線の出力が大きいほど、蒸着材料の供給量が多くなります。
図4a:強磁性の模式図。図4b:常磁性の模式図。各矢印が原子の磁化を表しています。
図5:元素周期律表。赤枠で囲まれた元素が5d遷移元素と呼ばれる。
図6:原子核の周りの電子の公転と自転によって生じる軌道磁気モーメントとスピン磁気モーメント。
図7a:トンネル磁気抵抗効果。絶縁層を挟む二つの強磁性体層の磁化の向きが平行の時に素子の抵抗は小さく、反平行の時には大きくなります。図7b: トンネル磁気抵抗素子は、HDDの磁気ヘッドなどに利用されています。
本件に関するお問い合わせ先
日本電信電話株式会社
先端技術総合研究所 広報担当
science_coretech-pr-ml@hco.ntt.co.jp
TEL:046-240-5157
東京大学
大学院理学系研究科・理学部 広報室
kouhou.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
TEL:03-5841-0654
ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
NTT STORY
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。