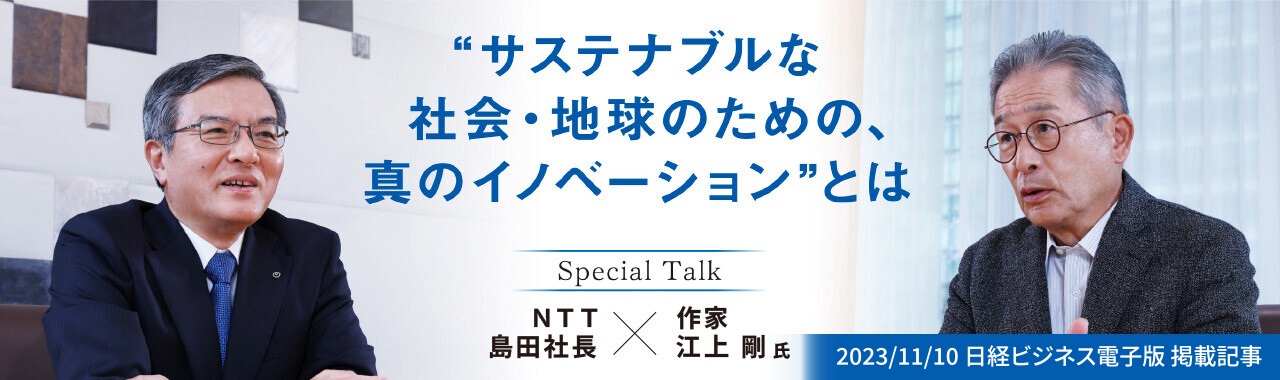<光量子コンピューター特集 全2回の第1部/第2部へ>
※ 本記事は、2025年2月27日 マイナビニュースに掲載された特集記事です。
みなさんは、「量子コンピュータ」と聞いてどんなものを想像しますか? おそらく「SF映画で出てきた未来のコンピュータ」、「よくわからないけれど、すごいことができそう」といったイメージを漠然と持っている方が多いのではないでしょうか。
現在、量子コンピュータは各国のテクノロジー企業によって研究が進められており、将来の完成が期待されています。そして、現在注目されているAIと同様に、社会を大きく進化させる可能性を秘めていることからビジネスパーソンが知っておきたい重要トピックです。
そもそも量子コンピュータとはどのようなコンピュータであり、私たちの生活にどのような豊かさをもたらすのか。今回、量子コンピュータの研究開発に携わるNTTグループの研究員の方々にお話を伺いました。
❇お話を伺った方々のプロフィール❇
- NTT先端集積デバイス研究所 准特別研究員
柏﨑貴大さん - NTT先端集積デバイス研究所 研究主任
井上飛鳥さん - NTT 研究企画部門 担当部長
白井大介さん - NTTコンピュータ&データサイエンス研究所 主席研究員
寺本純司さん
そもそも量子コンピュータってどんなもの?
 NTTの超高速光技術を活用した光量子コンピュータ向けデバイス(構成イメージ)
NTTの超高速光技術を活用した光量子コンピュータ向けデバイス(構成イメージ)
量子コンピュータとは、ざっくりとした言葉で表現すると「驚異的なスピードで計算(情報処理)を行うことができるコンピュータ」です。現在、世の中で使われている一般的なコンピュータの中でもトップの性能を持つ「スーパーコンピュータ」が10万年かけて解ける問題を、量子コンピュータは一瞬で解ける可能性があるそう。では、なぜそのようなスピードで計算できるのでしょうか。
「一般的なコンピュータは物理学用語でいう『古典力学』という現象を利用して動いています。古典力学とは、ボールを投げたら落ちるとか、壁に当たると跳ね返るといった、昔からよく知られている物理学のことです。一方で量子コンピュータは『量子力学』という仕組みで動作するコンピュータです」とNTT先端集積デバイス研究所の柏﨑貴大さんは説明してくれました。
量子力学は、100年ほど前に物理学者のアルベルト・アインシュタインをはじめとする多くの研究者が体系化した考え方で、物質を構成している「粒」をどんどん小さくしていったときに「波」のように振舞ったり、光などの「波」が「粒」のように振舞ったりする現象を見つけたのがはじまりと言われています。それは、古典力学では説明のつかない現象で、新しい物理学の領域として量子力学が始まったのだとか。
 量子力学について語る柏﨑貴大さん
量子力学について語る柏﨑貴大さん
そして、「古典力学」と「量子力学」では情報の扱い方が異なるそう。
NTT先端集積デバイス研究所の井上飛鳥さんは、「『古典力学』を用いたコンピュータは『0』と『1』で情報を取り扱います。例えば、たくさんデータがある中から特定のデータを見つけ出す計算を行う際は『00000』をチェック、それが違ったら次は『00001』をチェック、それも違ったら次は『00010』......というふうに繰り返し計算を行っていきます。一方、『量子力学』を用いたコンピュータは『0』と『1』を重ね合わせた状態を定義できる特長があり、計算を行う際、0かもしれないし1かもしれないという曖昧な状態のまま、一気に計算をすることができるのです」と解説しました。
 「古典力学」と「量子力学」の情報の扱い方を語る井上飛鳥さん
「古典力学」と「量子力学」の情報の扱い方を語る井上飛鳥さん
実は、古典力学を活用した従来のコンピュータでは、性能向上に伴う消費電力の増加などエネルギー面の課題があるほか、計算速度がいずれ頭打ちすることがわかってきています。「0」と「1」を重ね合わせた状態で扱うことができる量子コンピュータは、そうした限界を超えることができるため、現在さまざまな業界や企業などから期待されているのです。
〈ポイントまとめ〉
- 量子コンピュータとは驚異的なスピードで計算を行うことができるコンピュータ
- 「0」と「1」を重ね合わせた量子状態を活用することで高速に計算できる
自動運転や金融まで! あらゆる社会問題を解決できる時代がやってくる⁈
量子コンピュータが実現すると私たちの生活はどのように変わっていくのでしょうか。
NTTコンピュータ&データサイエンス研究所の寺本純司さんは、特に「最適化問題」の分野で活かせると考えているそうです。
「例えば、自動運転が今よりも浸透した世の中で、刻一刻と変わる交通状況を反映した自動運転ルートを導き出し、渋滞の無い、都市全体で最適化された世界を作ることや、さまざまな角度から金融のポートフォリオ分析を行い、最適な金融商品の選択ができる未来が実現する可能性があります」(寺本さん)

また、研究企画部門の白井大介さんは創薬分野での活用も期待できると考えています。現在AIを用いて行われている化学物質の組み合わせのシミュレーションが、量子コンピュータを活用することでより一層早くなり、創薬の開発も飛躍的に早まる可能性があるそう。
「その他、遺伝子情報などを用いて一人ひとりに最適化された薬を作り出すことも可能性として考えられています。オーダーメイドのため副作用もなく、未知の病気を防ぐ薬なども作れるようになるかもしれません」と白井さん。

さらに、「まだ遠い未来ですが、世の中そのものをシミュレーションすることも可能かもしれません。例えば、地球の天候を完全に再現し、異常気象などが起きた際に原因を量子コンピュータで分析するといった活用も期待されています」と述べました。
さまざまな社会問題を解決できる可能性を秘めている量子コンピュータですが、現在は研究・開発の段階にあります。GoogleやIBMといった海外のテクノロジー企業や、NTTグループをはじめとした国内の企業・大学などが研究を進めており、現状では「従来のコンピュータだと膨大な時間がかかる問題を一瞬で解ける」ことを証明できた段階とのことです。
量子コンピュータ研究の現状とNTTの技術力
量子コンピュータの実用化にあたり障壁となっているのが「誤り訂正」です。「誤り訂正」とは、「ノイズを検知して除去し、正解(理論的に可能な状態)に近づけること」をいいます。
柏﨑さんは、「量子はとても壊れやすく不安定です。そのため、現状の量子コンピュータは計算結果にノイズが入ってきてしまい、完全な正解ではなく、大まかに『このへんが正解だろう』という結果しか得られません。このノイズをどう除去するかに各社苦心しています」と解説してくれました。

現在開発が進んでいる量子コンピュータは、光や超伝導などを利用して「量子状態」を作り出し計算を行うそう。その中で、NTTでは「光量子コンピュータ」という光の波に情報をのせて処理を行う光通信の技術を使った量子コンピュータの研究を進めています。
超伝導方式で量子状態を保つには、絶対零度に限りなく近い温度にまで冷やす必要があり、大量の電力を必要とする大きな冷凍機がないと動かすことが出来ません。しかし、光量子コンピュータの場合、室温でも光量子が高速で飛び、光同士で量子もつれ状態を作るため冷凍機は必要なく、熱や気圧に対して強いという特長があります。この点から、光量子が大規模化や高速化の実現に近いとも言われており、光通信のノウハウをもつNTTでは、これまで開発してきた技術を活用しながら、光損失の少ない安定した光量子を生み出せるよう研究を進めているそうです。
〈量子もつれとは?〉
古典力学では説明できない現象で、2つ以上の量子が強い相関関係にあることをいいます。この量子もつれは、量子計算や量子通信などさまざまな量子技術のリソースとなり、セキュリティや次世代の量子ネットワークの基盤技術としての応用も期待されています。
 NTTが開発した量子光源モジュール
NTTが開発した量子光源モジュール
 NTTが開発した光量子コンピュータの心臓部「量子光源」のデモンストレーション
NTTが開発した光量子コンピュータの心臓部「量子光源」のデモンストレーション
そうした長年の研究が功を奏しNTTは、東京大学(東大)や理化学研究所(理研)と共同で、量子コンピュータの1号機を2024年11月8日にローンチ。その中でもNTTは特に、古典的な光から量子的な光を生み出し、また量子的な光から古典的な光へ変換することができる、高性能な「光パラメトリック増幅器」を開発しました。また、最新の結果では、量子もつれ状態の生成に関して従来よりも1,000倍以上高速化することに大きく貢献し、量子コンピュータ自身の高速化の可能性を示すことができたとしています。
量子コンピュータはいずれ社会のインフラとして定着していく
量子コンピュータ完成に向け、NTTグループではどのように未来を見据えているのでしょうか。
「よく量子コンピュータが完成する目処として2050年が挙げられますが、何を持って完成とするかというと、『誤り訂正ができて汎用的かつ大規模な量子コンピュータ』ができたときだと考えています。その実現には、光量子コンピュータ向けの光デバイスの性能向上が必要不可欠です」と語る井上さん。
「その中で光損失をできるだけ抑え、古典力学コンピュータのメモリに相当する『量子ビット数(量子の数)』をいかに増やせるデバイスを開発できるか。つまり、どれだけの情報を扱えるかが今後の研究テーマのひとつだと考えています」と柏﨑さん。
 NTTが掲げるロードマップ
NTTが掲げるロードマップ
具体的なロードマップとしては、同社がこれまで行ってきたビジネスとの親和性が高い「光の技術」を活用した量子コンピュータの実現を目指していき、2030年頃には実社会の役に立つ量子コンピュータの開発を実現させたいとしています。
そんな量子コンピュータについて井上さんは、「一家に一台のような存在ではなく、社会全体を支えるインフラのような使われ方をするのではないかと考えています。いつのまにか社会全体が量子コンピュータの恩恵を受けているような、そんな世の中がいつか来るのではないでしょうか」と語ってくれました。

社会を大きく変えるとされる量子コンピュータ。かつてはSF映画のように荒唐無稽な存在でしたが、技術の発展により実現が期待されるまでになっています。NTTは昨年、東大や理研と一緒に光量子コンピュータの1号機をローンチするなど、まさに量子コンピュータ研究で世界の最先端を行く存在。いつのまにか私たちの社会のインフラに量子コンピュータが取り入れられ、その恩恵を自然と受けられる日がいずれ来るのかもしれません。
<全2回の第1部/第2部へ>