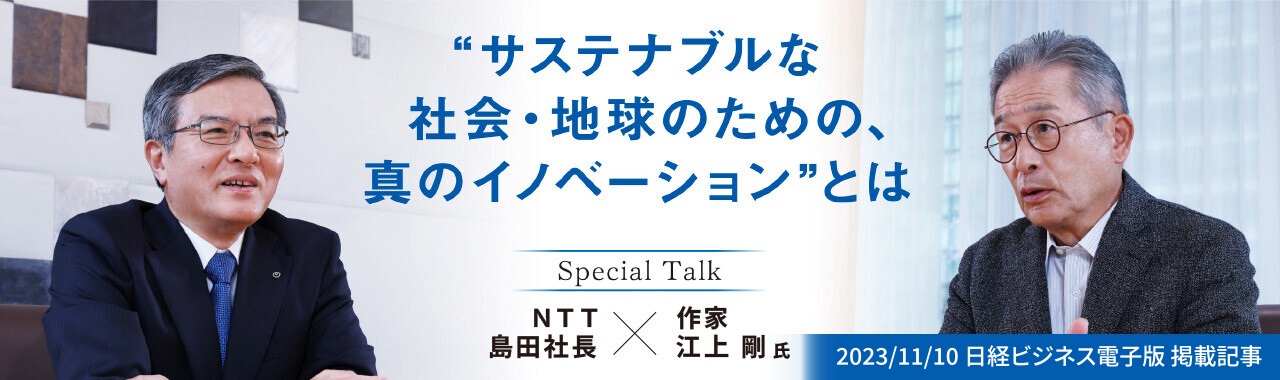NTTはスマートな世界の実現に向け、様々な研究所で研究開発活動を継続しています。毎年5月には茨城県の筑波研究開発センタで「つくばフォーラム」を、11月には東京都の武蔵野研究開発センタで「R&Dフォーラム」を開催するなど、NTTグループが取り組んでいる最先端の研究開発内容を公開しています。
海外でも2019年7月に米西海岸のシリコンバレーに米国での研究開発拠点となるNTTリサーチを開設しました。光技術や量子技術、暗号やヘルスケア領域の基礎研究などを海外の研究者と一緒に進め、NTTグループの海外展開を後押ししていくのが目的です。またグループの研究開発内容を海外に発信するため、NTTリサーチは毎年「Upgrade」というイベントを開催しており、今年も4月10-11日の2日間、サンフランシスコで開催しました。
イベントを現地で取材した(株)MM総研の関口和一代表取締役所長のレポートとしてお知らせします。
<全2回の第1部/第2部へ>
1) 「Upgrade2024」概要

米国におけるNTTの研究開発拠点であるNTTリサーチが4月10-11日の2日間、サンフランシスコで「Upgrade」と呼ばれる研究成果の公開イベントを開催した。2020年の開始から今年で4回目となるが、国内外から約700人が会場を訪れ、日本企業が米国で開くイベントとしては大きな賑わいを見せた。
シリコンバレーのサニーベールに本社を置くNTTリサーチは5-10年後の事業創造を目指した基礎研究を担っている。具体的な研究領域としては、次世代の情報通信基盤となる光技術や量子物理学、情報セキュリティを支える暗号情報理論やブロックチェーン技術、医療のデジタル化を促す生体情報処理技術の3つが柱だ。「Upgrade」のイベントもNTTリサーチが中心となって実施している。
会場はNTTが海外情報発信のためにサンフランシスコ市街に設けた「NTT XC(エクスペリエンスセンター)」を使い、26の展示ブースを開設した。内容的にはNTTリサーチが米国で進めている技術研究のほか、日本の研究所が取り組んでいる次世代光情報通信基盤の「IOWN」や生成AIの「tsuzumi」などを展示した。NTTコミュニケーションズやNTTデータの米国子会社、NTTデータサービスもサステナビリティや輸送モビリティサービス技術などを展示し、来場者の関心を呼んだ。
会期は2日間にわたり、初日はNTTリサーチの五味和洋CEOとNTT研究企画部門の荒金陽助IOWN推進室長が記者会見し、IOWNの高速通信ネットワーク「APN (All-Photonics Network)」を使って米国と英国それぞれの国内でデータセンターを超低遅延で接続する実験に成功したことを明らかにした。最近は環境問題や用地不足などから都市部でのデータセンターの開設が難しくなっており、「APNで都市部と郊外のデータセンターを結べば一体運用できるようになる」(荒金IOWN推進室長)という。
2日目には近隣の会議ホールで「Upgrade」の講演セッションが開かれた。開会挨拶に立った五味和洋NTTリサーチCEOは「飛行機やインターネットなどの発明が現実世界を"アップグレード"してきたが、その背後には常に重要な基礎研究の積み重ねがあった」と指摘、そうした基礎研究を米国で行うためNTTリサーチを2019年7月にシリコンバレーに開設したと説明した。
「Upgrade2024」の開催期間中に合間を縫って、講演セッションに登壇した五味和洋NTTリサーチCEOや川添雄彦 NTT 代表取締役副社長、木下真吾NTT 執行役員研究開発マーケティング本部研究企画部門長にNTTが目指す研究開発やNTTの強みなどについて聞いた。
2) 五味和洋 NTTリサーチ CEO インタビュー
- NTTの研究所をアメリカにつくった理由を教えて下さい。
五味 NTTの研究所には長い歴史があり、様々な成果を生み出してきましたが、もっと活性化し加速するにはグローバルな視点で研究者やパートナーを多様化する必要があると考えました。同時にNTTのグローバルビジネスが大きく伸びてきていますので、研究所としてもそれをサポートする体制が必要となりました。アメリカはそれらを効率的に実現するのに最適な場所です。NTTリサーチは設立から5年が経ちましたが、優秀な研究者を集めることができましたし、しっかりと成果も出ています。そういった意味では当初の目的はおおむね達成できたといえます。
- NTTリサーチが取り組んでいる研究内容についてお聞かせ下さい。
五味 3つのテーマがあります。いずれも基礎研究の分野になりますが、ひとつめは量子計算科学研究所(PHI Lab=Physics & Informatics Laboratories)」です。物理現象を使って新しい計算機をつくるのが大きな柱です。光の技術を使った新しい計算のメカニズムはIOWNとの親和性も高いです。2つめは暗号情報理論研究所(CIS Lab=Cryptography & Information Security Laboratories)」です。新しい暗号の方式を生み出したり、安全性を証明したりします。3つめは生体情報処理研究所(MEI Lab=Medical & Health Informatics Laboratories)」です。バイオデジタルツインの研究で、産業分野におけるデジタルツインの考え方を人間にも適用して人体をシミュレーションしていけば、医療現場が変わると考えています。
- グローバルで見ると研究所を手放した通信会社も多いですが、NTTが基礎研究を続けるのはなぜでしょうか。
五味 私はよく「NTTのDNAです」と言うのですが、技術を自分たちの中にしっかりと持って、サービスを作ったり提供したりできることが一番の価値だと考えています。技術を生み出し、その領域を引っ張って行く存在にならなければダメだろうと思っています。研究所を手放せばバランスシートは一瞬よく見えるでしょうが、技術を持ち続けることによって、他のグローバルキャリアから見ても、我々が明らかに全く異なる、強い立ち位置にいられるのではないかなと思います。
3) 川添雄彦 NTT 代表取締役副社長インタビュー
- NTTが研究開発に力を入れている理由を教えて下さい。年間30億ドルもの研究予算をかけているのは世界の通信会社でもNTTぐらいだと思いますが。
川添 世界の通信会社の中でもNTTは大きな研究所を今もまだ維持していることで非常にユニークな存在になってきたと実感しています。頑張って維持してきたからこそ、「IONW」や「tsuzumi」などが出てきたということだと思います。この流れをより強化していきたいと考えています。新しいビジネスを作っていくうえでは基礎的な研究開発が必要です。研究内容によってはすぐに社会にフィードバックできないものもありますが、それを維持していかないと次のネタがなくなってしまいます。研究所全体のバランスを見ながらマネジメントしていくことが非常に重要です。
- 「IOWN」はイギリスやアメリカ国内でそれぞれデータセンター間の接続実証実験に成功したと発表されましたが、現在の進展状況はいかがでしょうか。
川添 非常に順調に進んでいます。日本でも実証はできますが、国内に閉じて進めると世界的なアピールにはならないですよね。世界の色々なところで実証して、それを見てもらい理解してもらうことで、利用したいと考えるお客様がどんどん集まってくるという形につながればよいと思っています。
- ちょうど「Upgrade2024」の開催期間中に米東海岸で開催された日米首脳会談では政府間の合意文書にIOWNについての日米協力の言及があったということですが。
川添 日本を挙げて取り組むべきというアピールはIOWNを始めたときからずっとやってきました。それを積み重ねてきた結果だと思います。今回、これを日本の強みとしてアメリカとうまく歩調を合わせられるきっかけになったというのは非常に喜ばしいことです。アメリカがIOWNを世界に広げる重要なパートナーになってくれれば、一緒にこの技術を発展させていくことができます。日本だけで世界に広げていくのは大きなチャレンジであり、同時に大きなリスクも伴いますので、今後しっかりと進めていくうえで今回の合意文書にIOWNが入ったというのは本当に大きなことだと思っています。
4) 木下真吾 NTT 執行役員研究開発マーケティング本部研究企画部門長インタビュー
- 「Upgrade」のような研究開発のイベントを海外でやるということの狙いは何でしょうか。
木下 日本では武蔵野研究開発センタで年に1回、展示会を開いていますが、海外の方を直接お呼びするのはなかなか難しいので、NTTリサーチのあるこの場所で開催することで、より多くの海外の方に見ていただく機会をつくるのが狙いです。
- NTTの研究開発力の強みはどこにあるのでしょうか。特に「IOWN」など光技術と量子物理学に注力されているようですが。
木下 非常に多岐にわたって研究を行っている総合力が私たちの強みです。論文数のランキングではNTTは世界11位で、中でも光通信、音声認識、暗号、量子計算機の分野では世界1位です。
- その意味では光技術のIOWNは強みを一層活かせますね。
木下 NTTの光関連の技術は産業レベルだけではなく、学会レベルでも断トツに強い分野です。IOWNはコンピューティングの領域まで光を展開する技術ですが、長年続けているので他と比べてもノウハウの蓄積の差があります。
- 海外でのIOWNの広がりはいかがですか。
木下 IOWNグローバルフォーラムには現在約140社が参加していますが、海外企業からも多数参加してもらっています。今は(超高速ネットワークの)「APN」の通信の領域が先行していますが、コンピューティングの領域になるにつれ、どんどん広がっていくと思います。
- アメリカに基礎研究の拠点を設けるメリットは何ですか。
木下 MIT(マサチューセッツ工科大学)やスタンフォード大学などトップ大学との連携のしやすさがあります。実際にインターン生をNTTで受け入れたり、NTTの研究員を大学に派遣したりして共同研究をしています。そういった最先端の大学との強いコネクションを築いていくためには、アメリカに研究所があった方が進めやすいと考えています。
イベント初日の夕方には会場となったビルの屋上で歓迎レセプションが開かれ、東京から駆け付けた島田明社長が来場者に歓迎の言葉を述べた。「研究開発はNTTの歴史や文化であり、生成AIの「tsuzumi」を独自に開発できたのも40年間に及ぶNTTの言語処理技術研究のたまものだった」と強調し、レセプションに集まった多くの参加者から大きな拍手を浴びた。

<全2回の第1部/第2部へ>