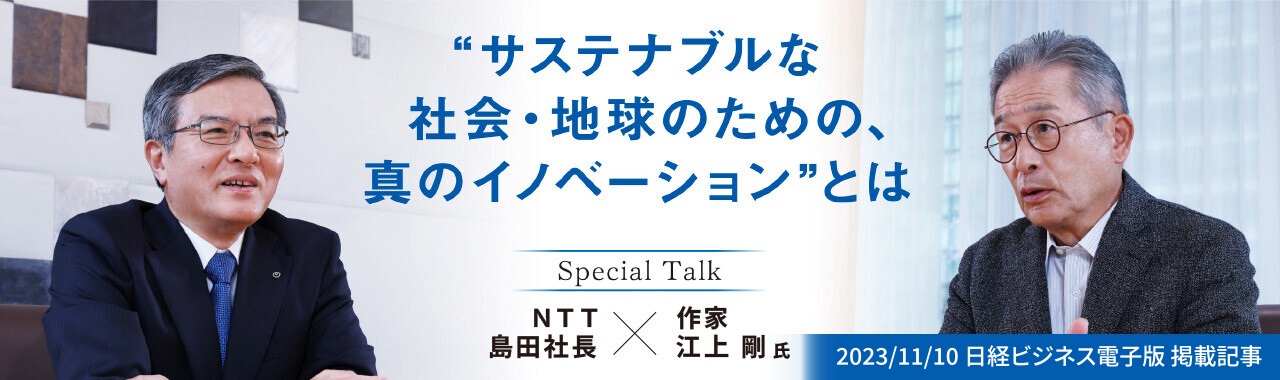NTTリサーチが4月10日から11日の2日間、サンフランシスコで開催したNTTグループの研究公開イベントの「Upgrade2024」 について、現地で開かれた記者会見や講演セッションなどの内容をご紹介します。
イベントを現地で取材した(株)MM総研の関口和一代表取締役所長のレポートとしてお知らせします。
<全2回の第2部/第1部へ>
1) NTTリサーチとNTT研究企画部門による記者会見

「Upgrade 2024」の講演セッションに先立ち、4月10日に五味和洋NTTリサーチCEOとNTT研究企画部門の荒金陽助IOWN推進室長による記者会見が行われた。最初に五味CEOからNTTの研究開発体制やNTTリサーチの概要、設立から5年間の取り組みについて説明があり、米ハーバード大学への新たな寄付活動についても発表があった。
五味CEOはまず「NTTは約2300人の研究者をグローバルで抱え、毎年約30億ドルを研究開発費に充てている」と説明。NTTリサーチは3つの研究所を持ち、5年間で86件の特許を出願中であることや、450本の学術論文が著名な研究雑誌や学会で発表されたことを紹介し、7件の最優秀論文が権威ある学会で受賞されたことも明らかにした。また基礎研究を推進するために、ハーバード大学やスタンフォード大学など世界的に著名な15の学術機関や組織とも協業していると述べた。
今回発表したハーバード大学への寄付活動では、同大学の脳科学センターの知性物理学(Physics of Intelligence)分野における奨学金制度にNTTが寄付することにしたと発表した。この寄付活動を通じてコンピューター科学や脳科学、心理学、物理学などの研究の橋渡し役を果たす考えだ。寄付金額は最大で170万ドル以上となり、博士研究員の支援などに使用される。
荒金IOWN推進室長からはIOWNの超高速ネットワーク「 APN(All-Photonics Network)」に関する説明とイギリスとアメリカで新たに始めたAPNの実証実験について発表があった。

生成AIなどの登場により、データセンターの需要が世界的に高まる中、環境問題や用地不足などから都市部でのデータセンターの開設が難しくなっていると荒金IOWN推進室長は指摘。地理的に離れた郊外のデータセンターでは遅延が発生することから、この問題を解決する手段として大容量、高品質、低消費電力、低遅延のAPNを活用するメリットを説明した。
APNについては日本では2023年に商用サービスを開始していることを紹介し、ユースケースとしてリアルタイムAI解析の遠隔処理を挙げ、自動運転などリアルタイムの応答が求められるサービスへの活用が有用であることを指摘した。
イギリスとアメリカではそれぞれ遠距離にあるデータセンターをAPNで接続する実証実験に成功したことを発表した。約100km離れたデータセンター同士をAPNで接続することで1ミリ秒以下の低遅延通信を実現し、分散型リアルタイムAI解析などへの利用可能性を確認したと述べた。従来のネットワークでは2ミリ秒を超える遅延が発生するという。
今後はIOWNのAPNをNTTデータとともにグローバルに展開し、金融分野をはじめ分散データセンター構築のユースケースづくりとなる共同実証実験を進めていくとこれからの計画を語った。
https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/04/12/240412a.html
2) 「Upgrade2024」の講演セッション

講演セッションで五味CEOの開会挨拶に次いで最初にパネル討論に登壇したのはNTTリサーチの3つめの研究分野にあたる生体情報処理研究チームを率いるディレクターのジョー・アレクサンダー氏(写真左)だ。心臓血管系の生態情報をセンサーで収集し、そのデータをもとに人間の健康状態を「バイオデジタルツイン」としてコンピューター上に再現できれば、「投薬や手術の準備など医療分野のデジタル化に大きく貢献できる」と強調した。

NTTの研究開発部門をつかさどる川添雄彦副社長(写真中央)も五味CEOと一緒にパネルに登壇し、NTTとしては次世代光情報通信基盤の「IOWN」や生成AI技術の「tsuzumi」などの開発に注力していると述べ、そのために年間30憶ドルにも上る研究開発予算を注ぎ込んでいることを明らかにした。
Upgradeのイベントが開幕した同じ日に米東海岸では岸田文雄首相とバイデン大統領との日米首脳会談が開かれ、日米両国の合意文書にIOWNにおける日米協力がうたわれたことを川添副社長が紹介。従来のシリコンチップ(半導体)によるコンピューターの時代を「フォトニックチップ(光半導体)が置き換えていくのではないか」と今後のデジタル社会を展望した。

講演セッションの分科会の最後には、光半導体などを実現する新しい技術「コヒーレント・イジング・マシーン(CIM)」などを研究する量子物理学研究チームのティム・マッケンナ氏が登壇した。光技術と量子物理学を融合することで「処理能力が現在のシリコンチップをはるかに上回る半導体の開発が可能になる」と指摘し、その回路基板をつくるのに「薄膜リチウムナイオベート(LN=ニオブ酸リチウム)」が有効であることを発見したという。マッケンナ氏は「薄膜LNの活用はまだ始まったばかりだが、2028年には20憶ドル市場に育つだろう」と予測した。

3) 量子物理学研究チームのティム・マッケンナ氏インタビュー
NTTリサーチで量子物理学チームを率いるディレクターのティム・マッケンナ氏に光半導体技術に関する研究内容について聞いた。
- 現在取り組んでいる研究について教えて下さい。
マッケンナ NTTリサーチでは私たちはコヒーレントな光コンピューターの開発に取り組んでいます。これはアナログコンピューターの一種であり、非常に難しい最適化問題の計算に有用です。その研究の一環としてリチウムナイオベート(ニオブ酸リチウム)の薄膜基板技術の開発を進めています。これは光半導体回路をつくるための基板で、次世代の光コンピューターを実現する技術です。
- NTTは次世代光情報通信基盤の「IOWN」構想を進めていますが、それを実現するための技術ということでしょうか。
マッケンナ その通りです。「IOWN」の高速ネットワークに搭載される光アクセラレーターとして利用ができ、それと同時にコンピューター同士をつなぐ際の通信技術としても非常に有効です。将来的には演算も通信も光でできるようになり、シームレスなオール光ネットワークができます。
- 今、生成AIが話題となっていますが、そうした技術にも活用できるのでしょうか。
マッケンナ それはいい質問です。生成AIはすべての技術の需要を拡大しました。生成AIのニーズに応えていくにはすべてのエコシステムが進化を遂げる必要があります。将来はもっと優秀なハードウエアが必要となります。今のハードウエアでは十分に対応することができません。電子の技術も今後進化するとは思いますが、光ネットワークの方が明らかに進んでいくでしょう。その意味では私たちが現在取り組んでいる「IOWN」が果たす役割は非常に大きいと思っています。
<全2回の第2部/第1部へ>