2019年6月 7日
横浜市建築局
東京急行電鉄株式会社
株式会社NTTドコモ
日本電信電話株式会社
横浜市、東急電鉄、NTTドコモ、NTTが、住民主体のまちづくりの活動をICT・IoT技術で加速する新たな取り組み「データ循環型のリビングラボ」共同実証実験を開始 ~次世代郊外まちづくりにおけるまちの課題解決・コミュニティ活性化をめざして~
横浜市、東京急行電鉄株式会社(以下、東急電鉄)、株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)、日本電信電話株式会社(以下、NTT)は、横浜市と東急電鉄が推進する「次世代郊外まちづくり※1」のモデル地区「たまプラーザ駅北側地区」(以下、本地区)において、地域住民との連携のもと、まちの課題解決やコミュニティ活性化を目的に、新たな取り組みとなる「データ循環型のリビングラボ(以下、本スキーム)」に関する共同実証実験(以下、本実験)を、2019年6月15日(土)から開始します。
本スキームは、まちに関するデータを活用し、地域住民が主体となり、まちの課題解決に向けた取り組みを行うことを支援・加速する仕組みです。本実験では、地域住民が設定した地域課題「コミュニティ活性化」に対して、「まち歩きサービス」と「地域チャットボット」という2つのICTサービス(以下、ICTサービス)を提供し、その活用を通じて住民の関心ごとや活動エリア、まちのイベント情報などのまちに関するデータを収集します。そして、収集データを地域住民に共有し、ワークショップなどで活用することで、ICTサービスの導入に向けた検討・検証を行います。さらに、データを可視化して共有することで、新たなまちの課題や住民のニーズに気づくきっかけをつくり、地域住民による新たな活動の創出をめざします(図1・2)。
また本実験を開始する2019年6月15日(土)に、多くの方々の参加促進を目的として、地域住民向けのキックオフイベントを実施し、概要を説明するとともに、実際にICTサービスを体験できる機会を設けます。
本実験の概要
1.目的
(1)本地区における地域の課題解決やコミュニティ活性化
(2)本スキームの有効性や、ICTサービス・ワークショップ手法の有用性検証
2.期間
2019年6月15日(土)~2020年3月16日(月)
3.対象地域・対象者
| 対象地域 | たまプラーザ駅北側地区(横浜市青葉区美しが丘1・2・3丁目) |
|---|---|
| 対象者 | 本地区に在住・在勤、もしくは本地区で活動されている方々など |
4.実施項目(詳細は別紙参照)
(1)本スキームの検証
| 検証内容 | 本スキームが住民主体の活動を生み出す効果、データを活用したワークショップが住民の議論を活性化する効果など |
|---|
(2)ICTサービスの検証
| <1>楽しく安全にまちを歩くためのまち歩きサービス | まちの情報や写真をデジタル地図上に投稿することで、住民のおすすめスポットやバリアフリー情報などを可視化・共有し、楽しく安全なまち歩きを通じて、コミュニティ活性化を図ります。 |
|---|---|
| <2>地域のローカル情報を提供するチャットボット | 地域のローカルな情報に特化したチャットボットサービスで、暮らしに役立つ情報やイベント情報などを、テキストの会話形式で提供します。コミュニティ活性化を図るとともに、投稿された質問内容などの分析で、住民の関心ごとやお困りごとを明らかにします。 |
| 検証内容 | サービス導入可能性・持続可能性、まちのデータの可視化・共有の効果など |
5.背景と経緯
横浜市と東急電鉄は、2012年4月から産学公民の連携・協働による「次世代郊外まちづくり」に取り組んでいます。情報発信・活動拠点「さんかくBASE(WISE Living Lab)※2」で、2017年から地域住民とともに「リビングラボ勉強会」を開催するなど、住民が主体的にまちの課題を解決する手法「リビングラボ※3」を実践しており、東京大学の小泉秀樹教授などとも連携しています。本実験もリビングラボの一環です。
ドコモとNTTは、まちのデータを収集・可視化してコミュニティ活性化につなげる「IoTスマートライフ※4」や、住民と企業が共創するリビングラボの研究など、住民主体のまちづくりに資するICT・IoT技術の開発や研究を進めてきました。また本実験は、横浜市とNTTが締結している「官民データ活用による超スマート社会の実現に関する包括連携協定※5」の取り組みの一環としても実施します。
今般、ドコモとNTTが、次世代郊外まちづくりの取り組みによって住民主体のまちづくりが進んでいる本地区に注目し、連携のメリットを感じたことから、4者共同で本実験の検討を始め、地域団体や地域住民の方々との対話も行った上で、本実験に取り組むこととなりました。
6.今後について
本実験の結果を踏まえ、4者は地域住民とともに、2021年頃のICTサービスの本格導入に向けて、検討を進めます。また、本実験で得た知見を活かし、横浜市と東急電鉄は、地域住民との共創によるリビングラボの取り組みを展開し、持続可能なまちづくりやSDGsの実現を推進します。ドコモとNTTは、ICTやIoT技術を活用した住民主体のまちづくりの仕組みや住民とのサービス共創手法の確立をめざします。
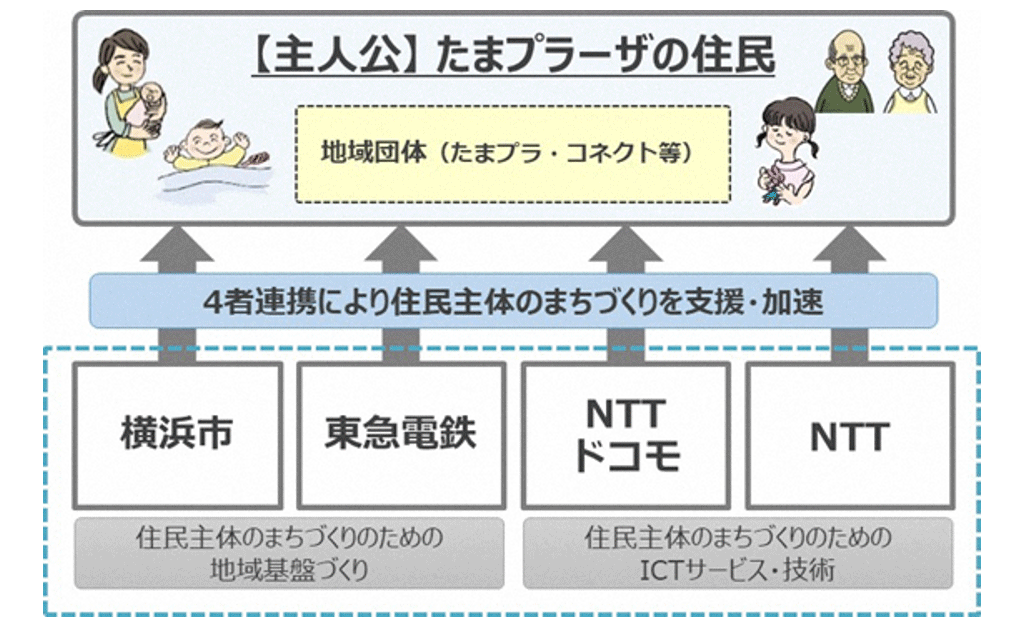 図1 本実験の連携体制イメージ
図1 本実験の連携体制イメージ
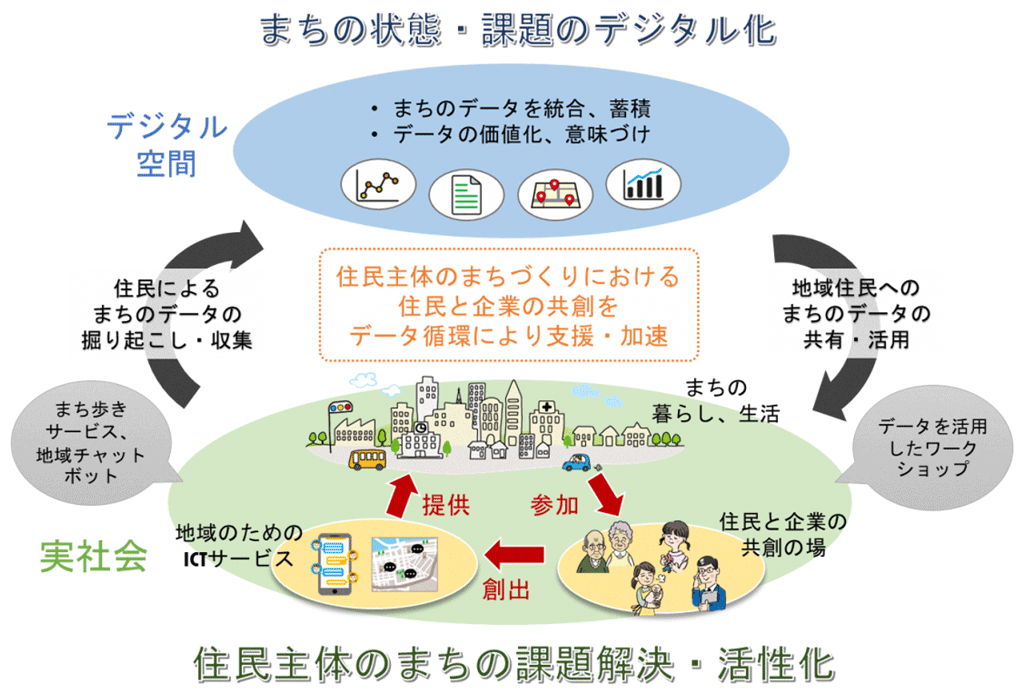 図2 「データ循環型のリビングラボ」イメージ
図2 「データ循環型のリビングラボ」イメージ
詳細は別紙の通りです。
別紙
実験概要について
(1)本スキームの検証
(1-1)データ循環型のリビングラボの仕組みの検証
本スキームは、住民が主体的にまちのデータを収集・共有・活用するサイクルにより、まちの課題解決・活性化のための住民と企業の共創活動(リビングラボ)を支援・加速する仕組みです。本スキームでは、まちに関するデータの可視化と住民への共有・活用が進むことで、まちの課題解決・活性化のための議論や活動をより効果的にすることが期待できます。これは、従来のリビングラボにはない新たな価値を提供可能な仕組みであり、本実験では、本スキームの有効性や構築可能性を検証します(図3)。
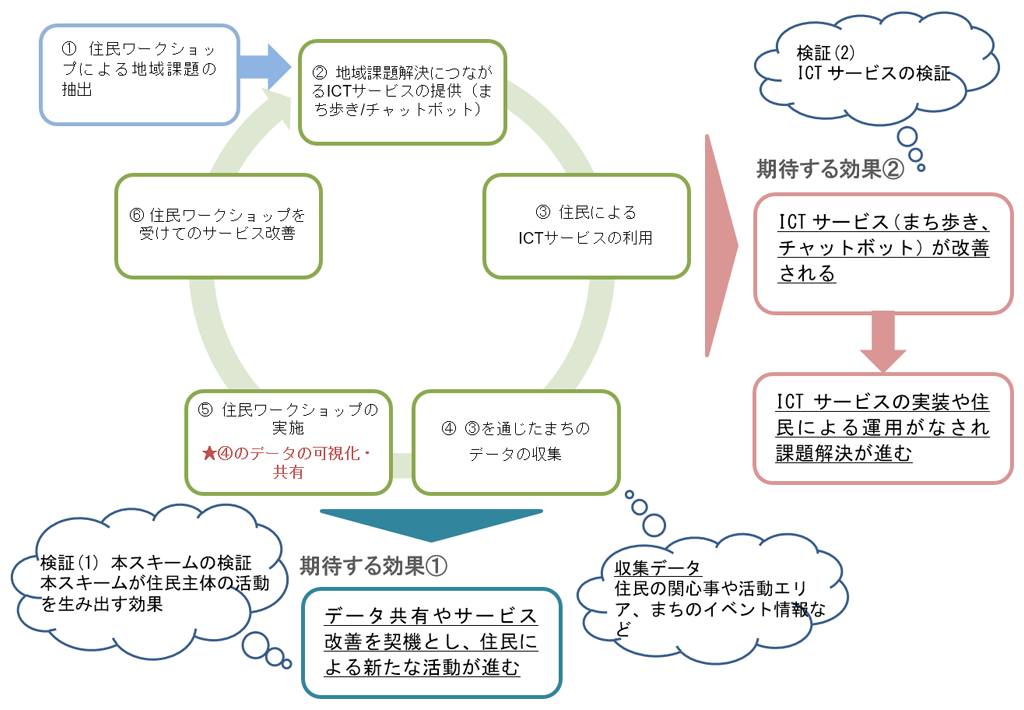 図3 本実験フローイメージ
図3 本実験フローイメージ
(1-2)まちのデータを活用した住民主体のワークショップ手法とデータ活用効果の検証
本実験では、サービスを通じて収集するデータを活用した「データ活用型デザイン手法」を用いて、まちをよりよくするための住民参加型ワークショップを実施します。本手法は、サービスづくりの過程をゲーム化する「ICTデザインゲーム※6」を活用した手法であり、課題分析やアイデア発想の経験が少ない人であっても容易かつ平等に、データを活用したサービス検討過程に参加することが可能になります。また、ICTサービスを通じて収集したまちのデータを可視化することで、住民が自分たちのまちや活動について知らなかったことに気づくきっかけを与え、まちの活性化に関する議論や検討を加速することを狙います(図4)。
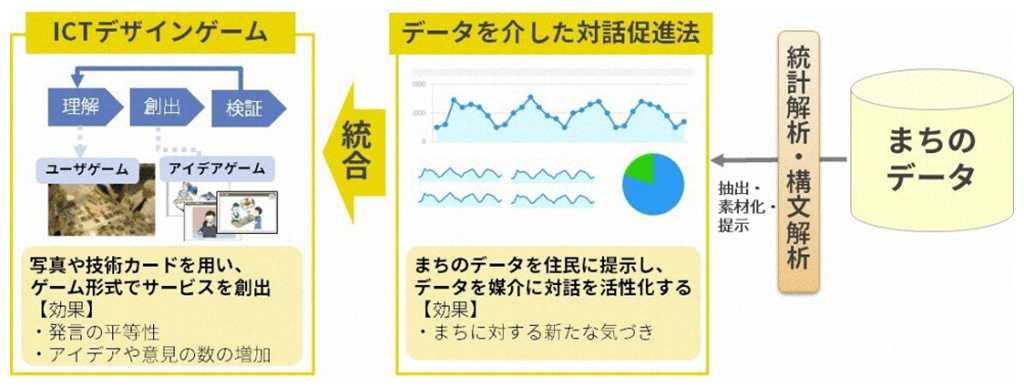 図4 データ活用型共創デザイン手法のイメージ
図4 データ活用型共創デザイン手法のイメージ
(2)ICTサービスの検証
本実験に先駆け、地域団体「たまプラ・コネクト※7」が中心となり、地域住民の対話の場を設け、「コミュニティの活性化」を解決すべき課題として設定しました。本実験では、「コミュニティの活性化」をめざすサービスとして、「(a)楽しく安全にまちを歩くためのまち歩きサービス」と「(b)地域のローカル情報を提供するチャットボット」を導入し、住民が主体的にまちのデータの可視化・共有を行えるようにします。また、たまプラ・コネクトを中心に、住民の方々と連携し、これらサービスの地域への導入・活用に向けた検証・検討を実施します。
(a)楽しく安全にまちを歩くためのまち歩きサービス
まち歩きサービスは、まちの写真をデジタルな地図上に投稿する「スポット投稿機能」により、おすすめスポット情報を共有するサービスです。さらに、フィットネスリストバンド※8の併用により、利用者の歩数、歩行距離、消費カロリーなどの活動量の可視化や共有が可能になります(図5)。また、まちの段差や階段などのバリアフリー情報を住民が投稿する技術(MaPiece®※9)も合わせて活用します。まちのスポット情報、利用者の活動量やバリアフリー情報などのデータを収集・共有することで、楽しく安全なまち歩きとそれを通じた住民コミュニティ活性化を実現します。

図5 まち歩きサービスのイメージ
(b)地域のローカル情報を提供するチャットボット
本実験では、地域のローカルな情報に特化したチャットボットサービス(以下、地域チャットボット)を地域住民とともに製作します。地域チャットボットは、地域での暮らしに役立つ情報やイベント情報などを、テキストの会話形式で提供するサービスです(図6)。Webでは見つけづらいような地域のローカルな情報を住民から集め、多くの住民が気軽に情報にアクセスできるようにします。また、チャットボットへ投稿された質問内容などを分析することで、住民の方々の関心ごとやお困りごとを明らかにします。
さらに、地域住民の持つスキルやコミュニティ活動に関する情報も収集・共有するなど、チャットボットが地域で持続的に利用されるための仕組みも検討します。
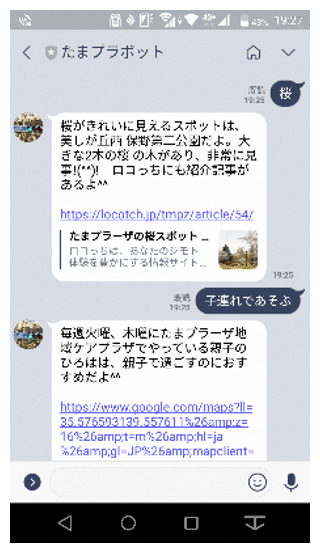
図6 地域チャットボットのイメージ
キックオフイベントについて
地域の住民の方々に、概要を理解いただき、本実験に参加いただくために、2019年6月15日(土)にキックオフイベントを実施します。
イベント概要
| 日時 | 2019年6月15日(土)11:00~12:00 |
|---|---|
| 会場 | WISE Living Lab 共創スペース(住所:神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目23番1,3) |
| プログラム | <1>本実験の目的・内容について <2>4者の取り組み意義について <3>住民の方々が本実験に期待すること(企画や準備に携わる住民の方々より発表) <4>ICTサービスのデモ体験 <5>ワークショップ~本実験でやってみたいこと~ |
参考
「SDGs未来都市・横浜」について

横浜市は2018年6月に、SDGsの達成に向けて優れた取り組みを提案する都市「SDGs未来都市」と、その中で特に先駆的な取り組みをする「自治体SDGsモデル事業」に選定されました。「環境を軸に、経済や文化・芸術による新たな価値・賑わいを創出し続ける都市の実現」をビジョンに、SDGs未来都市の大都市モデルに挑戦しています。

本事業はSDGsの17のゴールのうち、主に上記のゴールとの関係を意識したものとしています。
用語解説
※1次世代郊外まちづくり:横浜市と東急電鉄が2012年4月に締結、2017年4月に更新した「『次世代郊外まちづくり』の推進に関する協定」に基づき、田園都市線沿線の住宅地=「既存のまち」を舞台に、大都市近郊の郊外住宅地が抱えているさまざまな課題を、地域住民・行政・大学・民間事業者の連携・協働によって解決していく、従来にはない住民参加型・課題解決型のプロジェクト。
http://jisedaikogai.jp
次世代郊外まちづくりの活動拠点・情報発信の場として、2017年5月に整備された東急電鉄が運営する施設。産学公民の新しい連携のあり方によるイノベーションの創出や、地域住民の自発的なコミュニケーションの形成を促す取り組みを行う「共創スペース」に加え、コミュニケーション、ワークショップなどのスペースやカフェも併設。
http://sankaku-base.style/
地域住民をサービス共創パートナーと捉え、住民の実生活環境の中で本質的な課題の探索や発見、解決策の検討や検証を行う仕組み。 ※4IoTスマートライフ:
IoT技術を用いて、人々の活動やまちの状態などのあらゆるデータを統合し、価値化することで、コミュニティやまちが活性化し、人々のいきいきとした生活の実現をめざす、ドコモを中心とした取り組み。 ※5官民データ活用による超スマート社会の実現に関する包括連携協定:
健康・福祉、子育て・教育などさまざまな分野で、データ活用を通じて市民生活をより便利にしていくこと、および、データを重視した政策形成の取り組みを通じて市政を効率的・効果的に運営していくことを目的とした、横浜市、横浜市立大学、NTTが2018年に締結した包括連携協定。 ※6ICTデザインゲーム:
サービスの検討過程を「ゲーム化」することで、課題分析やアイデア発想などに慣れていない方でも、短時間で効率的にサービスアイデアを創出できる手法。 ※7たまプラ・コネクト:
2014年10月に、次世代郊外まちづくり「住民創発プロジェクト」から生まれた、たまプラーザのまちづくりに関心をもつ人やグループをつなぐ地域団体。2015年9月に合同会社を設立。企業との協働による地域共助システムのプロトタイピングや勉強会、レクリエーション、交流会などを実施。
http://tama-pla.net/
利用者の睡眠時間、就寝時刻、起床時刻や歩数、歩行距離、消費カロリーなどを自動計測するデバイス。 ※9MaPiece®:
車いすやベビーカーで移動される方などへの道案内(ナビゲーション)に必要なバリアフリー情報の収集技術 【参考】車いす利用者への道案内に必要なバリアフリー情報を市民参加により自動的/持続的に収集する技術MaPiece®(まっぴーす)を開発。
https://www.ntt.co.jp/jp/newsrelease/2018/11/22/181122b.html
(参考) 本日、この資料は国土交通記者会、横浜市政記者会、横浜経済記者クラブ、ときわクラブ、総務省記者クラブ宛にお届けしています。
本件に関するお問い合わせ先
横浜市
建築局 住宅部 住宅再生課 担当課長 加藤忠義
Tel:045-671-4458
株式会社NTTドコモ
広報部 豊田・李
Tel:03-5156-1366
日本電信電話株式会社
サービスイノベーション総合研究所 企画部広報担当
Tel:046-859-2032
ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
NTT STORY
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。















