生物多様性
方針・考え方
NTTグループの事業に欠かせない通信設備、特に電柱、通信ケーブルなどは自然環境の中に設置しており、生態系に対し少なからず影響をおよぼしています。また、通信ケーブルなどがリスやカラスによってかじられ破損するなど、生態系から影響を受けることもあります。生物多様性を含む生態系からの恵み(水や食料など)は、人類を含む生物全体にとって不可欠なものであり、その保全に向け考える必要があります。
ありのままの自然を未来に引き継ぐために、NTTグループは事業活動および社員活動を通して、サプライヤー、パートナーの皆さまとともに、自然に寄り添い、森林破壊の防止や生物多様性に関する取組み(自然資本への配慮)を推進します。
NTTグループは生物多様性の保全を重要課題と位置づけ、国際的に認知された「緩和階層(回避・最小化・回復・相殺)」の考え方を踏まえ、事業活動による生物多様性への影響を最小限に抑える取り組みを推進しています。例えば、再生可能エネルギー新設時は環境影響評価法等に定められる環境影響評価(環境アセスメント)の実施、各生態系(動植物)への影響調査・評価を行い、リスクの特定および回避(風力発電で猛禽類の衝突防止、鳥類・哺乳類等の生態へも配慮した開発及び維持管理の実施)を行い、自然への影響の緩和策を実施しております。
また、NTTグループは、生物多様性の保全を重要課題の一つと位置づけております。自社およびサプライチェーンにおける事業活動において、世界的または国内的に重要な生物多様性が存在する地域に近接する地域に隣接した場所での事業事業活動を回避すること(生物多様性保全への配慮)をNTTグループサプライチェーンサステナビリティ推進ガイドラインに記載しています。
取組み事例①:自然資本モニタリング
2025年3月にバイオームならびにドコモビジネス、ドコモソリューションズ、データ、ドコモにて、リモートセンシングによる植生および生物の広域推定技術の開発に着手しました。
衛星画像データ解析技術をはじめとするNTTグループのアセットおよびバイオームが保有する国内最大級1000万件以上のリアルタイム生物データベース「BiomeDB」を掛け合わせることで、生物多様性のモニタリングを支援するための広域かつ継続的な植生および生物の関連データ収集・分析手段を確立し、 生物多様性への影響を最小限に抑える取り組みを推進し、社会のネイチャーポジティブ実現に貢献します。

取組み事例②:生物多様性中期ロードマップの策定
ドコモでは「2030年ネイチャーポジティブ」および「2050年自然と共生する世界」への貢献に向けた取り組みをロードマップ化し推進しています。通信設備周辺の生物多様性配慮(基地局周辺での生物多様性配慮施策、基地局設置時のステークホルダーエンゲージメントの強化、その他通信設備周辺でのステークホルダー参加型生物多様性保全)、鉱物資源への対応(サプライヤへの働きかけ、資源循環の促進)、自社アセットの活用(ICT活用、地域拠点参画)などを通じ、生物多様性保全活動を強化すると共に、森林破壊の防止にもつなげていきます。
推進体制
生物多様性を含む「NTTグループサステナビリティ憲章」のNTTが考える持続可能な社会における3つのテーマ・9つのチャレンジに基づくアクティビティ(重要課題)については、サステナビリティ委員会での審議・取締役会での承認を経て、選定・見直しを行っています。
目標と実績
サステナビリティ指標
※横スクロールできます
| 項目 | 2024年度目標値 | 2024年度実績値 | 2025年度目標値 |
|---|---|---|---|
⑤自然保護地区に設置した事業用設備の数および全体に占める割合 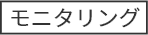 |
モニタリングのため無し | 設備数:913拠点 全体に占める割合:4.6% |
モニタリングのため無し |
⑥水リスク地域に設置した事業用設備の数および全体に占める割合 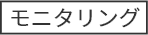 |
モニタリングのため無し | 設備数:23拠点 全体に占める割合 :0.4% |
モニタリングのため無し |
バウンダリ:NTT連結子会社
当年度は、事業用設備のスクリーニング調査の概要を記載しつつ、リスクついてはTCFDに追加する形で開示拡充、機会についてはICTを活用したソリューション事例等を開示していく方向で検討を進めています。
開示ができていない指標および目標については、 TNFD勧告で示されているコア・メトリクスや欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)等を踏まえ、今後検討を進めていきます。
主な取組み
自然資本関連の分析
NTTグループでは通信事業をはじめ、データセンター、再生可能エネルギー事業など幅広いセグメントで事業活動を行っています。以下のプロセスで、NTTグループの自然への関わりを分析しました。

Step1:事業用設備 種類別 依存・影響の把握

TNFDが推奨するLEAPアプローチに則り、事業用設備を対象に自然関連の影響・依存について分析を 行うために事業用設備の中でも特に売上に与える影響の大きいサービス群を提供する設備に絞り、基地局、 通信設備、データセンター設備での依存・影響を把握した後、リスクの顕在化を確認し評価を行いました。
ENCORE※による一般的な評価結果に基づき、実施各事業がどのような生態系サービスや自然資本に 依存し影響を与えているかに関する評価結果をヒートマップで可視化を実施しました。

※ENCORE: Natural Capital Finance Alliance(NCFA)が世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCMC)と共同で開発したTNFDで も紹介されている依存と影響分析オンラインツール
ENCOREの評価結果をもとに、依存と影響の重要な項目として、以下を認識しました。
| 依存 |
|
|---|---|
| 影響 |
|
※影響への対応についてはStep2にて記載します
Step2:影響への対応(リスク確認)

影響の重要性を踏まえ、ENCOREにより特定した基地局とデータセンターに加え、建築面積1,000㎡ 以上の通信設備、自然への影響が大きい再生可能エネルギー(太陽光・風力発電)設備に対して生物多様性の保全や水利用による影響度を確認しました。
①生物多様性の保全
事業用設備のうち自然への影響が大きいと考えられる基地局※1・通信設備・データセンター設備の約2 万拠点を対象に、KBA※2をもとにスクリーニングし、深掘り調査を行いました。
再生可能エネルギー(太陽光・風力発電)設備は、前年度同様に想定される自然への依存・影響が大きいと考えられるため、施工会社にヒアリングを行い影響リスクへの対応を確認しました。
※1地上から30M以上の位置にアンテナが設置してある基地局
※2Key Biodiversity Areas、生物多様性重点地域
②水利用
データセンターに対し、主に「Aqueduct」※3及び「ThinkHazard!」※4という分析ツールを用いて、水ストレス評価を実施し、「Extremely High」「High」となる拠点の深掘り調査を行い影響を確認しました。
※3世界資源研究所により開発された、水リスクに関する評価ツール
※4GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery) が世界銀行グループなどの組織と協同して開発したツール
Step3:調査結果


①生物多様性の保全
深掘り調査を行った基地局・通信設備については、各施設の影響として周辺生態系への懸念事象が生じていないか把握するため、各市町村自治体への問い合わせにより現状把握を行いました。結果、対象設備に関して懸念事象はなく、事業上生じうるリスクは限定的と判断しています。
再生可能エネルギー(太陽光・風力発電)設備においては、環境影響評価法等に定められる環境影響評価(環境アセスメント)を実施し、各生態系(動植物)への影響調査・評価を行っています。環境影響評価手続きでは、配慮書、方法書、準備書、評価書の4段階で審査を受けながら進め、結果は法令に基づく一定期間、各社のHPで公表しています。また、風力発電では施設への猛禽類の衝突について調査・予測・評価を行っており、運転開始した案件(またはプロジェクト)においては専門家からの指導・助言を仰ぎながら長期的な観察を行い、鳥類・哺乳類等の生態へも配慮した開発及び維持管理を実施しています。
②水利用
分析の結果、3つの拠点が水を消費する水冷式のデータセンターであり、かつ水ストレスが非常に高いとされている地域に位置していることがわかりました。
当該データセンターについて詳細を確認したところ、南アジアの2か所については現状では地下水を取水していますが、現在、現地水道事業者によって表流水を用いた水道の拡張計画が進んでいることから今後は水道水源への移行が考えられ、地下水源に依存している水供給に関するリスクは低減される見込みです。
あわせて、水ストレス地域に立地する該当施設の状況を踏まえ、地域や環境への影響を最小限に抑えるための取水量削減に向けた工夫や対策の検討を進めます。
また、もう1か所については、水供給事業者が排水の再生水を活用しており操業地域における水資源に十分に配慮していることが確認できています。
原材料調達
金属原料の採掘段階における自然関連リスクの概要把握
NTTグループでは、サプライチェーン全体(上流・下流)でのリスク管理として、金属資源の採掘地に関する生物多様性リスク・水リスクの状況を調査しています。
金属材料の採掘段階については、主要な金属として銅、鉄、アルミニウム、レアメタルの4種を取り上げ、日本への輸出が多い主要産出国における主要鉱山について、立地を生物多様性リスク・水リスクの観点から評価することで実施しました。これらの結果、生物多様性リスクは非常に多くの鉱山で高リスクであること、水リスクも半数程度の鉱山でリスクが高く、自然への大きな影響を与えうることが分かりました。
NTTグループでは、サプライチェーンにおいて持続可能な社会の実現に向けた取組みを進めていくため、サプライヤーに対し、「NTTグループサプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン」及び「NTTグループグリーン調達基準」の遵守を依頼し、定期的に環境保全に関する取組状況についてアンケート・調査等を行うほか、企業評価や製品評価を実施しています。今後、これらの枠組の中で、自然・生物多様性保全に関するサプライヤーとの対話を強化し、金属資源の採掘を含む上流工程における、生物多様性の保全や地域の水資源の保全に関する取組強化を検討します。
主要な金属資源の採掘地に関する生物多様性リスク・水リスクの状況
※横スクロールできます
| 金属種類 | 使用する主な設備 | 生物多様性リスクが高い地域への立地割合 | 水ストレスが高い地域への立地割合 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 電線、電気通信設備 | 91.7% | 41.7% |
| 鉄 | 鉄塔、アンテナ、建築材料 | 93.8% | 12.5% |
| アルミニウム | 鉄塔、アンテナ | 84.6% | 69.2% |
| レアメタル(タンタル) | 電子部品 | 85.7% | 57.1% |
| 計 | 89.6% | 41.7% | |
(備考)
生物多様性リスク: 生物多様性リスク評価ツール(IBAT)を用い、70km圏内にKBA・保護地域がある場合に高リスクとした。
水ストレス: WRI Aqueduct 2019を使用し、Baseline Water Stressにおける「High」「Very High」とされた生産拠点を高リスクとした。
なお、割合は、金属種類ごとの調査拠点数(主要産出国における主要鉱山)を分母とした割合。レアメタルについては、主要統計における拠点情報の入手可能性をふまえ、また通信事業における電子部品原料を念頭に、タンタルを選定した。
サステナビリティに関する重要項目のリスクや機会については、サステナビリティ委員会に付議し、取締役会に報告しています。
なお、NTTグループのリスク管理プロセスとして、身近に潜在するリスクの発生を予想・予防し、万一リスクが顕在化した場合でも損失を最小限に抑えること等を目的として、リスクマネジメントの基本的事項を定めたリスクマネジメント規程を制定し、代表取締役副社長が委員長を務めるビジネスリスクマネジメント推進委員会及びグループビジネスリスクマネジメント推進委員会が中心となって、リスクマネジメントのPDCAサイクルを構築し運用しており、サステナビリティ関連のリスクの識別、評価、管理に関するプロセスはNTTグループの総合的なリスク管理プロセスに統合されています。
森林破壊防止への取り組み
資源有効活用の観点としても、レアメタルは新たに鉱山から採掘するよりも、使用済み製品からリサイクルすることで効率的に回収できる資源です。NTTグループでは、ドコモを中心に「ケータイリサイクル」活動を推進し、全国のドコモショップなどを通じて使用済み携帯電話の回収・再資源化に取り組んでいます。これにより、レアメタルの再利用を促進するとともに、新規採掘に伴う森林伐採や生態系破壊などの環境負荷の低減に貢献しています。
また、2023年度ドコモ泉南堀河の森(大阪府)が環境省「自然共生サイト」へ認定されました。大阪南部地域の里地里山に成立する自然豊かな環境と、そこに生息するオオムラサキや二ホンヒキガエルなどのさまざまな生き物、生態系を守る活動を実施しています。
2025年度にもドコモ土岐の森(岐阜県)、ドコモ四国 土佐・いの 元気の森(高知県)が新たに認定されるなど取組みを進めており、2027年度までに全国で5か所の自然共生サイト認定をめざします。
生物多様性保全への貢献、循環型社会への転換
NTTグループでは生物多様性や循環型社会への関心の高まりは新たなビジネスの機会になるものと考えています。事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献していきます。引き続き、生物多様性及び資源循環についてNTTグループのリスク及び機会の検証に努め、情報開示を続けていきます。
森林保全
森林保全のための技術変革を積極的に進めていくことで、二酸化炭素吸収量の増加や生態系及び水資源の保全・保護を推進し持続可能な社会の実現に貢献します。林業における省人化及び自動化による下刈りコストの軽減を目的とした自動運転型下刈機械の植栽フィールド運用実証(以下、本実証)を実施しています。本実証では、林業における省人化及び自動化による下刈りコスト軽減を目的に開発した自動運転型下刈機械を使用し、林業現場で実際に下刈りを行い、その運用性能を検証します。機械の操作は、自動運転ルートの設定と車両の遠隔監視を行う専用アプリケーションがインストールされたタブレット端末一つで実施します。

森林由来J-クレジットの創出・審査・取引支援
住友林業株式会社とNTTドコモビジネスは、2024年8月から「森林価値創造プラットフォーム」(以下「森かち」)を提供しています。「森かち」は、森林由来J-クレジット※1の創出・審査・取引を包括的に支援するプラットフォームです。日本で初めて※2森林クレジットの創出者・審査機関・購入者それぞれに対して地理情報システム(GIS※3) の機能を提供することで発行プロセスの効率化とクレジットの信頼性向上を実現し、森林クレジットの創出・流通活性化をめざします。
※1森林由来J-クレジットとは、間伐などの森林の適切な管理を行うことによるCO2吸収量をクレジットとして国が認証したものです。
※2両社調べ
※3GISとは、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術です。

NTT STORY
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。














