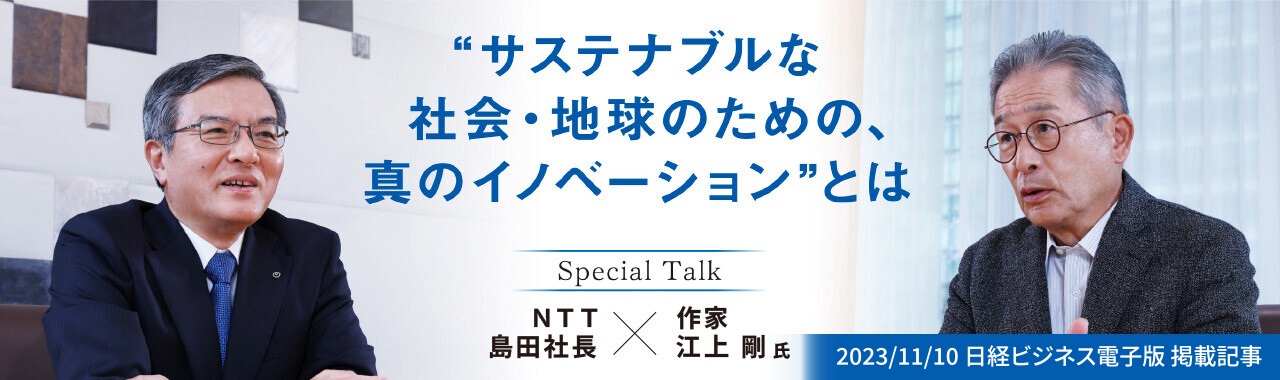米国南部テキサス州のダラスで10月初旬、次世代光通信基盤「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」の国際推進組織「IOWN Global Forum」の中間メンバー会議と情報発信イベント「Futures(フューチャーズ)」が開かれた。ダラスに本社を置く米通信大手、AT&Tの研究所幹部やデータセンター技術の国際標準化組織「OCP(Open Compute Project)」の責任者らが講演し、フォーラムに対し米国のIT業界が関心を示し始めたことを印象づけた。現地を取材した(株)MM総研の関口和一代表取締役所長のリポートとしてお知らせします。
光接続の国際標準化組織がIOWNに関心示す
 フォーラム会場では様々な機器も展示された
フォーラム会場では様々な機器も展示された
「生成AI時代を迎えた今、AT&Tがめざすオープンな光通信技術を推進するにはIOWN Global Forumとの協力関係が重要になる」。オープニングセッションではAT&T研究所でネットワーク基盤技術を担うジョン・ギボンズAssistant Vice Presidentが講演、IOWNの技術に対し強い関心を示した。AT&Tはベライゾンと並び、米国の通信市場を二分する巨大通信会社で、生成AIの登場に伴うデータセンター需要をにらみ、通信網の光化を急いでいる。2015年には「Open ROADM MSA」と呼ぶ光伝送装置の標準化組織を起ち上げ、複数のベンダー間でオープンな光接続を実現しようとしている。
 AT&T研究所 ジョン・ギボンズAssistant Vice President
AT&T研究所 ジョン・ギボンズAssistant Vice President
オープニングセッションにはテキサス大学ダラス校でOpen ROADMを研究するアンドレア・フマガリ教授も登壇し、「IOWNがめざすオープンなAPN(All-Photonics Network)はOpen ROADMとの親和性が高い」と指摘した。テキサス大学ダラス校はAT&Tの光技術の開発を後押ししており、これまでノキアやエリクソンなど北欧の通信機器メーカーと日本や台湾などアジアのIT企業を中心に進めてきたIOWN構想に米国の通信業界が新たな技術パートナーとして名乗りを挙げたことを意味する。
IOWN Global ForumはNTT、ソニーグループ、米インテルの3社で2020年1月にスタートし、現在は通信会社やメーカー、ユーザー企業など約170社・団体が名を連ねている。今回のダラス会議には世界の約60社・団体から約250人のメンバーが一堂に会し、米国におけるフォーラムの存在感をアピールした。
 テキサス大学ダラス校 フマガリ教授
テキサス大学ダラス校 フマガリ教授
データセンターの国際標準化組織もIOWNと連携へ
オープニングセッションにはデータセンターやクラウド技術の国際標準化組織「OCP」のCIO(イノベーション・オフィサー)、クリフ・グロスナー氏も登壇し、「生成AIの広がりに伴う電力需要に対応するにはIOWN Global ForumとOCPが互いに協力する必要がある」と訴えた。OCPは米メタ(旧フェイスブック)を中心に2011年にスタートした標準化組織で、今年8月に台湾で開かれた同団体のイベント「OCP APAC Summit」にNTTの荒金陽助IOWN推進室長がフォーラムの代表として講演に招かれたのがきっかけで両者に密接な関係が生まれた。
そうしたお膳立てを務めたのが日本の産業技術総合研究所(産総研)に相当する台湾の「ITRI(工業技術研究院)」や台湾のIT企業だった。というのもフォーラムはIOWNの推進団体ではあるが、技術実装の標準化組織ではないため、IOWNの実装をめざすにはOCPのような技術実装の標準化組織を巻き込んでおく必要があると考えたようだ。OCPにはメタのほか、グーグルやマイクロソフト、インテル、AMD、NVIDIA、シーゲイトといった米国の有力IT企業がメンバーとして参加しており、IOWNの認知度が米国のIT業界でも高まりつつあることを表している。
グロスナー氏によると、OCPには米国企業以外にも英半導体技術会社のARMや韓国のサムスン電子など世界約500社・団体が名を連ねており、2025年時点のメンバーの世界総売上高は約1070億ドル(約17兆円)に上るという。「2029年には1900億ドル(約29兆円)まで伸びる見通しだ」と語り、OCPとの関係構築はIOWN Global Forumにとっても大きなチャンスになると指摘した。
 OCPのグロスナーCIO
OCPのグロスナーCIO
生成AIの登場が低消費電力技術への関心促す
今回の会議ではフォーラムの中間メンバー会議とは別にフォーラムの活動成果を発表する公開セッション「Futures」も開かれた。NTTの川添雄彦チーフエグゼクティブフェローがフォーラム会長として開会挨拶に立ち、「生成AIの登場がIOWNの低消費電力技術に対する関心を大きく促した」と指摘した。フォーラムがスタートした2020年はちょうど新型コロナウィルスの感染拡大が始まった時期で、「当時はオンライン会議やリモートワークなどのネットワーク需要が大きく高まったが、2022年11月に米オープンAIがChatGPTを投入したことでAIブームに火が付き、IOWNへの期待がさらに高まった」と川添氏はいう。
フォーラムではIOWNの様々なPOC(概念実証)を進めているが、その成果も発表された。日本では9月後半に「世界陸上競技選手権大会(世界陸上)」が開催され、報道を担当したTBSテレビがIOWNによる放送番組のリモート制作技術で様々な競技を放映した。スポーツ中継にはこれまで競技会場に大きな中継車を持ち込み、車内で映像素材を編集してから放送局に送っていたが、APNを活用することで映像素材をそのまま放送局に伝送し、局側で編集作業ができるようになった。これにより中継車にかかるコストが削減され、編集作業の自由度も大きく高まった。
ほかにも金融機関向けデータセンターの地域分散化や生成AIに利用されるGPU(画像処理半導体)データセンターの共同利用などのPOCも成果を挙げている。金融機関向データセンターは証券取引所などがある都市部に置く必要があったが、APNを活用すれば電力コストの安い地方に設備を配置するなどデータセンターの分散化が可能になる。GPUデータセンターもAPN接続により複数企業で設備を共同利用できる。
 IOWN Global ForumにおいてPresident and Chairpersonを務める
IOWN Global ForumにおいてPresident and Chairpersonを務める
NTT チーフエグゼクティブフェロー 川添雄彦
建設現場や倉庫・配送業が新たなユースケースに
さらに注目を浴びた新しいPOCが建設現場や倉庫・配送業などにおけるIOWNの活用だ。超低遅延のAPNにより、建設機械を遠隔操作したり、建設現場に光回線を敷設して定期点検などを遠隔で行ったりできるようになる。倉庫・配送業ではロジスティクスをネットワークでリアルタイム管理したり、AGV(無人搬送車)を正確に走らせたりすることが可能になるという。フォーラムの責任者を務めるNTTの川島正久氏は「POCには投資対効果をしっかりと見極めるテクノ・エコノミック・アナリシス(技術経済分析)の観点が重要だ」と強調し、フォーラムでも常にそうした観点からPOCを進めていると語った。
IOWN Global Forumは、日本では情報通信関連企業だけでなく、様々なユーザー企業がメンバーに加わっている。こうした様々なユースケースが登場したことで、海外においてもユーザー企業の関心が高まっており、米大手証券会社のモルガン・スタンレーなど新たなメンバーがフォーラムに加わった。川島氏は「IOWNはもはや日本の技術ではなく、グローバルに受け入れられつつある」という。
今回のイベントでは10月半ばまで日本で開催された「大阪・関西万博」でのIOWNの様々な活用法も披露され、参加者の関心を呼んだ。IOWN Global Forumは活動開始から5年半を迎え、折り返し地点を過ぎたことで、今後の活動に拍車がかかる見通しだが、ダラス会議で米IT業界がIOWNに対し関心を寄せたことは大きな弾みとなりそうだ。
 IOWN Global ForumにおいてTechnology Working GroupのChairを務める
IOWN Global ForumにおいてTechnology Working GroupのChairを務める
NTT 研究企画部門 IOWN推進室 川島正久
(役職は取材時点のものです)
■関連リンク
IOWN構想とは
https://group.ntt/jp/group/iown/
IOWN Global Forumとは
https://group.ntt/jp/group/iown/outreach.html
離陸期迎えた「IOWN構想」
https://group.ntt/jp/magazine/blog/iown_grobal_forum/
キーパーソンが語る、IOWN離陸に必要なこと
https://group.ntt/jp/magazine/blog/iown_grobal_forum_report/
折り返し地点迎えたIOWN、ストックホルムで5周年総会
https://group.ntt/jp/magazine/blog/igf_stockholm/