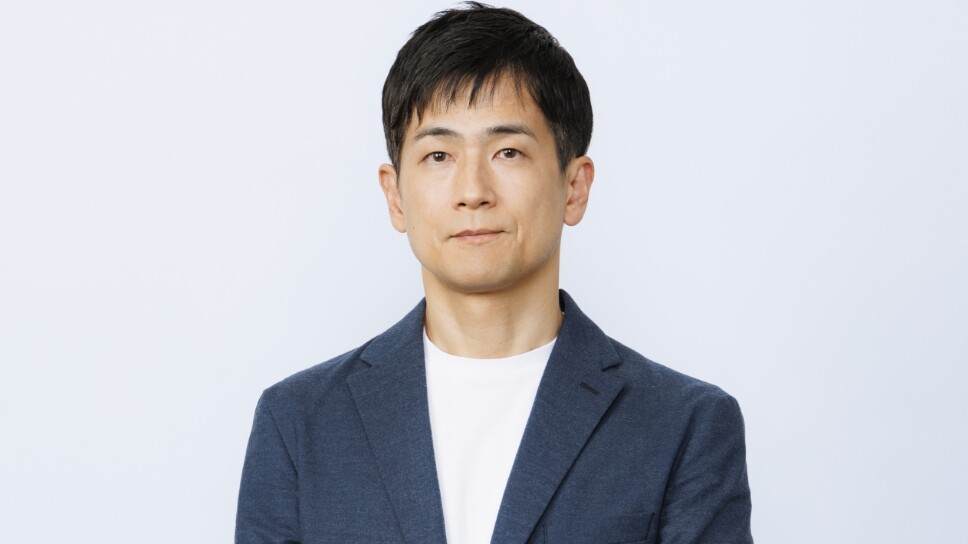NTTグループは、
社会のサステナビリティを
追求します。
サステナビリティ
NTTが考える持続可能な社会の実現のため、NTTグループは社会のサステナビリティを追求します。
-

マネジメントメッセージ
NTTグループの持株会社であるNTT株式会社代表取締役社長のメッセージをお届けします。
-

サステナビリティマネジメント
持続可能な社会を実現していく上で、私たちNTTグループは、Self as Weという考えを基本に据えています。
NTT
MATERIALITY
ESGデータ・資料
NTTグループ各社CSRサイトへのリンク
NTTグループ各社のCSR活動はこちらよりご覧ください。
NTT STORY
NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。